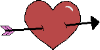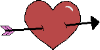|
|
|
|
پ@گوڈT‚حپA•œٹˆ‚جƒCƒGƒX—l‚ةڈo‰ï‚ء‚½چإڈ‰‚جڈطگl‚ئ‚µ‚ؤƒ}ƒOƒ_ƒ‰‚جƒ}ƒٹƒA‚ج‚¨کb‚ً‚µ‚ـ‚µ‚½پBچ،“ْ‚ح”قڈ—‚جکb‚ًڈ‚µ•â‘«‚µ‚ـ‚µ‚ؤپA‚»‚ê‚©‚çژں‚ج‚¨کb‚ةگi‚ف‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
پ@ƒ}ƒOƒ_ƒ‰‚جƒ}ƒٹƒA‚ھ•œٹˆ‚جژهپAƒCƒGƒX—l‚ة‚¨‰ï‚¢‚µ‚½‚ج‚حپAƒCƒGƒX—l‚ھڈ\ژڑ‰ثڈم‚إ‘§‚ًˆّ‚«ژو‚ç‚êپA‘’‚ç‚ê‚ؤ‚©‚çژO“ْ–ع‚جپA“ْ—j“ْ‚ج’©‘پ‚‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پBژہ‚ح‚±‚ج‚ئ‚ح‚ئ‚ؤ‚à‘هگط‚ب‚±‚ئ‚إ‚ ‚è‚ـ‚µ‚ؤپAچ،“ْپAگ¢ٹE’†‚ة‚ ‚éƒLƒٹƒXƒg‚ج‹³‰ï‚ھ“ْ—j“ْ‚ج’©‚ة—ç”q‚ًژç‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚حپA‚±‚ج‚±‚ئ‚ة—R—ˆ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ي‚¯‚إ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@ƒ}ƒOƒ_ƒ‰‚جƒ}ƒٹƒA‚حپAگ¹ڈ‘‚ة‚و‚è‚ـ‚·‚ئپAژµ‚آ‚جˆ«—ى‚ةژو‚èœك‚©‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ئڈ‘‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBژ„‚ھژq‚ا‚à‚جچ پAƒIƒJƒ‹ƒgپEƒuپ[ƒ€‚ج‰خ•t‚¯–ً‚ئ‚ب‚ء‚½پuƒGƒNƒ\ƒVƒXƒgپv‚ئ‚¢‚¤‹°•|‰f‰و‚ھ—¬چs‚è‚ـ‚µ‚½پBƒٹپ[ƒKƒ“‚ئ‚¢‚¤ڈ—‚جژq‚ةژو‚èœك‚¢‚½ˆ«—ى‚ئˆ«–‚•¥‚¢‚جگ_•ƒ‚ھ‘خŒˆ‚ً‚µ‚ؤپAڈ—‚جژq‚ً‹~‚¢ڈo‚·‚ئ‚¢‚¤“à—e‚¾‚ء‚½‚ئژv‚¢‚ـ‚·پBˆ«—ى‚ةœكˆث‚³‚ꂽƒٹپ[ƒKƒ“‚ح‚ف‚é‚ف‚éŒ`‘ٹ‚ھ•د‚ي‚èپA–ع‚ًŒ©ٹJ‚«پAگ؛‚à‹°‚낵‚°‚بˆ«–‚‚جگ؛‚ة‚ب‚èپAژٌ‚ھ360“x‚®‚é‚è‚ئ‰ٌ‚ء‚½‚肵‚ؤپAژ„‚ح‚ ‚ـ‚è‚ج‹°•|‚ة‰½“x‚à‚©‚ش‚ء‚ؤ‚¢‚½–Xژq‚إ–ع‚ً•¢‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚µ‚©‚µپAگ¹ڈ‘‚إˆ«—ى‚ةژو‚èœك‚©‚ê‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپAŒˆ‚µ‚ؤ‚±‚¤‚¢‚¤‚±‚ئ‚ًŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پB
پ@گ¹ڈ‘‚إ‚¢‚¤ˆ«—ى‚ئ‚حپAگ¸گ_•a‚ج‚±‚ئ‚¾‚ئگà–¾‚·‚éگl‚à‚¢‚ـ‚·پBژ„‚حپA‚»‚ê‚àˆل‚¤‚ئژv‚¤‚ج‚إ‚·پBگ¸گ_•a‚جگl‚ھˆ«—ى‚ةœك‚©‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚حŒ¾‚¦‚ب‚¢‚µپAگ¸گ_•a‚إ‚ب‚¢گl‚ھˆ«—ى‚ةœك‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ئ‚حŒ¾‚¦‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پBˆ«—ى‚حپAژè’i‚ئ‚µ‚ؤگlٹش‚جگg‘ج‚âگS‚ًڈP‚¢پAگl‚ً•a‹C‚ة‚³‚¹‚邱‚ئ‚à‚ ‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB‚µ‚©‚µپA‚·‚ׂؤ‚ج•a‹C‚ھˆ«—ى‚جژd‹ئ‚¾‚ئ‚حŒ¾‚¢گط‚邱‚ئ‚ح‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپBˆ«—ى‚ج–ع“I‚ح‚à‚ء‚ئگ[‚¢‚ئ‚±‚ëپA‚آ‚ـ‚èژ„’B‚جگlٹi‚ة“ü‚èچ‚ٌ‚إپA‚»‚ê‚ًژx”z‚µپA”j‰َ‚·‚邱‚ئ‚ة‚ ‚é‚ج‚إ‚·پB
پ@‚½‚ئ‚¦‚خ“ْ–{‚إ‚حپu‹S‚ة‚ب‚éپv‚ئ‚¢‚¤•\Œ»‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBŒƒ‚µ‚¢‘‚µ‚ف‚ة•ك‚ç‚ي‚ê‚ؤ•œڈQ‚ج‹S‚ة‚ب‚é‚ئ‚©پA‘¼‚ج‚±‚ئ‚ًˆêگطŒع‚ف‚ب‚¢ژdژ–‚ج‹S‚ة‚ب‚é‚ئ‚©پAگlٹش‚ئ‚حچl‚¦‚ç‚ê‚ب‚¢‚و‚¤‚بژc‹s‚³‚ً‚à‚ء‚½ژEگl‹S‚ة‚ب‚é‚ئ‚©¥¥¥¥پB‚±‚ج‚و‚¤‚ةگlٹش‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA‚ـ‚ء‚½‚گl‚ھ•د‚ي‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚±‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚»‚ê‚حپAŒƒ‚µ‚¢‘‚µ‚فپA—}‚¦‚ھ‚½‚¢—~–]پAژ•ژ~‚ك‚ج—ک‚©‚ب‚¢ژv‚¢ڈم‚ھ‚èپA‚»‚¤‚¢‚ء‚½‚à‚ج‚ھژ„’B‚جگlٹi‚ة“ü‚èچ‚ٌ‚إپA‚ا‚¤‚µ‚و‚¤‚à‚ب‚¢‚ظ‚ا‚ةژx”z‚µپA”j‰َ‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚±‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤˆّ‚«‹N‚±‚³‚ê‚é‚ج‚إ‚·پB‚ ‚é‚¢‚ح‹ة“x‚جژ©گM‘rژ¸پA’ê‚ب‚µ‚ج”ك‚µ‚فپA•sˆہپA‚»‚¤‚¢‚ء‚½‚à‚ج‚ة”›‚ç‚ê‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤپAژ©–\ژ©ٹü‚ة‚ب‚ء‚½‚èپAژ©ژEٹè–]‚ةژو‚èœك‚©‚ꂽ‚èپAŒ»ژہ“¦”ً‚ةٹׂ邱‚ئ‚à‚ ‚è‚ـ‚·پBàب‹^گS‚ةژو‚èœك‚©‚ꂽگlٹشپAچغŒہ‚ج‚ب‚¢•sˆہ‚ةژو‚èœك‚©‚ꂽگlٹشپA‚±‚ج‚و‚¤‚ةژ„‚ا‚à‚جگlٹi‚ھ‰َ‚µپAچك‚â‹°‚êپAگâ–]‚â‹^‚¢‚ة”›‚ç‚ꂽگlٹش‚ة‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚±‚ئ‚±‚»ˆ«—ى‚جژd‹ئ‚¾‚ئپAژ„‚حچl‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@‚à‚؟‚ë‚ٌپA‚»‚ê‚حگl‚ً‚à”ٌڈي‚ة‹ê‚µ‚ك‚ـ‚·‚ھپAژ©•ھژ©گg‚à‘ٹ“–‚ة‹ê‚µ‚¢‚±‚ئ‚ةˆل‚¢‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پBˆمٹw“I‚بژ،—أ‚إ–ü‚³‚ê‚é‚ي‚¯‚إ‚à‚ب‚پAگlٹش“I‚بˆ¤‚â—م‚ـ‚µ‚إ—§‚؟’¼‚ê‚é‚ي‚¯‚إ‚à‚ب‚پA’N‚ة‚àژè‚ھ‚آ‚¯‚ç‚ê‚ب‚¢پA‚ا‚¤‚ة‚àژè‚ھ‚آ‚¯‚ç‚ê‚ب‚¢گlٹش‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚إ‚·پBƒ}ƒOƒ_ƒ‰‚جƒ}ƒٹƒA‚حژµ‚آ‚جˆ«—ى‚ةژو‚èœك‚©‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚¢‚¤‚ج‚إ‚·‚©‚çپA‚»‚ج‹ê‚µ‚ف‚ج‚¢‚©‚خ‚©‚è‚ج‚à‚ج‚إ‚ ‚ء‚½‚±‚ئ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پBژ„’B‚ج‘z‘œ‚ً’´‚¦‚½‘ه‚«‚ب‹ê‚µ‚ف‚إ‚ ‚ء‚½‚ةˆل‚¢‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
پ@‚µ‚©‚µپA‚»‚ج‚و‚¤‚بژ–‚حپAژ„’B‚ة‰ڈ‚ج‚ب‚¢کb‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پBژ„’B‚جچ°‚حپAˆ«—ى‚ج‚و‚¤‚ب‹C–،‚جˆ«‚¢‚à‚ج‚ةگI‚ـ‚ê‚邱‚ئ‚ح‚ب‚¢پA‚ـ‚ء‚ئ‚¤‚بچ°‚¾‚ئŒ¾‚¢گط‚ê‚é‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پBƒNƒٹƒXƒ`ƒƒƒ“Œ€چى‰ئ‚جچ‚“°—v‚ئ‚¢‚¤•û‚ھپAƒ}ƒOƒ_ƒ‰‚جƒ}ƒٹƒA‚ةژv‚¢‚ًٹٌ‚¹‚ؤ‚±‚ٌ‚ب•¶ڈح‚ًڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@پu‚¾‚ê‚جگS‚ج‚ب‚©‚ة‚àپA‹°‚炉œ’ê‚ةپA‚ذ‚ئ‚آ‚ج•ھگg‚ئ‚µ‚ؤƒ}ƒOƒ_ƒ‰‚جƒ}ƒٹƒ„‚ھگ±‚ٌ‚إ‚¢‚éپB’p‚¸‚ׂ«پAڈء‚µ‚و‚¤‚ج‚ب‚¢‰ك‹ژ‚ً”é‚©‚ة•ّ‚¦‚±‚ٌ‚إپA‚ا‚¤‚µ‚و‚¤‚à‚ب‚گS‚¤‚ب‚¾‚ê‚ؤ‚¢‚éƒ}ƒٹƒ„¥¥¥¥پBگ¢‚جژ¯ژزپAŒ«گl‚©‚ç•ج‚ـ‚³‚ê‘a‚ـ‚ê‹s‚°‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚خ‚©‚è‚إ‚ب‚پA’‡ٹش‚ئ‚à‚¢‚¤‚ׂ«–¯ڈO‚©‚ç‚à’ـ‚ح‚¶‚«‚ة‚³‚ê”nژ‚ة‚³‚ê“¥‚ف‚آ‚¯‚ة‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éƒ}ƒٹƒ„¥¥¥¥پB‚³‚ç‚ةپAچإŒم‚ةمv‚è‚آ‚±‚¤‚ئ‚µ‚ؤپA‚ذ‚ê•ڑ‚µ‚ؤçW‚èٹٌ‚éپA‹~‚¢‚جڈêڈٹپAگ_“a‚©‚ç‚à‘aٹO‚³‚ê‚ؤپA‚ا‚±‚ة‚àچs‚‚ׂ«ڈٹپA—ٹ‚é‚ׂ«ڈٹپAٹٌ‚é‚ׂ«ڈٹ‚ًژ¸‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚éƒ}ƒOƒ_ƒ‰‚جƒ}ƒٹƒA¥¥¥¥پB
پ@ڈ‚ب‚‚ئ‚àژ„‚حپA‹~‚¢‚و‚¤‚ج‚ب‚¢پA’p‚¸‚ׂ«پA‘إ‚؟‚ذ‚µ‚ھ‚ꂽƒ}ƒOƒ_ƒ‰‚جƒ}ƒٹƒ„‚ًپAژ„‚ج“à•”‚ةپA”غ‚ف‚ھ‚½‚پA‚©‚©‚¦ژ‚ء‚ؤ‚¢‚éپBگط‚èٹü‚ؤ‚邱‚ئ‚àپA–³ژ‹‚·‚邱‚ئ‚àپA‹~m‚·‚邱‚ئ‚àˆ×‚µ‚¦‚ب‚¢‚إپA‚ذ‚½‚·‚çپA’p•”‚ئ‚µ‚ؤپA‚©‚©‚¦‚±‚ـ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپvپiگخˆن”üژ÷ژqپAپwƒ}ƒOƒ_ƒ‰‚جƒ}ƒٹƒ„پxپj
پ@ژ„‚àپAچ‚“°—v‚³‚ٌ‚ئ‚ـ‚ء‚½‚“¯ٹ´‚ب‚ج‚إ‚·پB‚»‚µ‚ؤپA‚±‚ج‚و‚¤‚بƒ}ƒOƒ_ƒ‰‚جƒ}ƒٹƒA‚ھپA‹~‚¢ژهƒCƒGƒX—l‚ئ‰i‰“‚جمJ‚ةŒ‹‚خ‚ꂽڈo—ˆژ–پA‚»‚ê‚ھ•œٹˆ‚جƒCƒGƒX—l‚ئ‚جڈo‰ï‚¢‚¾‚ء‚½‚ج‚إ‚·پB‚»‚ج‚و‚¤‚ب–{“–‚ة‘fگ°‚炵‚¢ڈo—ˆژ–‚ھپA“ْ—j“ْ‚ج’©‚ة‹N‚±‚ء‚½پBژ„’B‚ھ“ْ—j“ْ‚ج’©‚²‚ئ‚ة—ç”q‚ًژç‚é‚ج‚حپA‚»‚ج‚±‚ئ‚ًŒج‚ب‚ج‚إ‚·پBژ„’B‚à‚ـ‚½پAƒ}ƒOƒ_ƒ‰‚جƒ}ƒٹƒA‚ئ‹¤‚ةپA‚»‚ج‚و‚¤‚ب‹~‚¢ژه‚ئ‚جڈo‰ï‚¢پA‚ـ‚½‰i‰“‚جمJ‚ج’†‚ةڈµ‚©‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئگM‚¶‚é‚©‚ç‚ب‚ج‚إ‚·پBپ@ |
|
|
|
|
|
پ@‚³‚ؤپAژں‚ب‚邨کb‚حپA‚»‚ج“ْ—j“ْ‚ج—[‚ׂج‚±‚ئ‚إ‚ ‚è‚ـ‚·پBچrگى‹³‰ï‚ح’©‚ج—ç”q‚ئ‹¤‚ةپA—[‚ׂج—ç”q‚ًژç‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚±‚ê‚حچrگى‹³‰ï‚ةŒہ‚ء‚½‚±‚ئ‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB—[‚ׂج—ç”q‚à‚ـ‚½‘½‚‚ج‹³‰ï‚ھ‘هگط‚ةژç‚ء‚ؤ‚«‚½—ç”q‚جژٹش‚ب‚ج‚إ‚·پB
پ@گ¹ڈ‘‚ة‚و‚è‚ـ‚·‚ئپAƒ}ƒOƒ_ƒ‰‚جƒ}ƒٹƒA‚ھ•œٹˆ‚جژه‚ة‚¨‰ï‚¢‚µ‚½‚»‚ج“ْ—j“ْ‚ج—[‚×پA“ٌگl‚ج’يژq‚ھƒGƒ‹ƒTƒŒƒ€‚©‚çƒGƒ}ƒI‚ةŒü‚©‚ء‚ؤ•à‚¢‚ؤ‚¢‚½پA‚ئ‚ ‚è‚ـ‚·پBˆêگl‚حƒNƒŒƒIƒp‚ئ‚¢‚¤پA‚±‚±‚¾‚¯‚ةڈo‚ؤ‚‚é’يژq‚إ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚à‚¤ˆêگl‚ج’يژq‚ح–¼‘O‚ھ‚ب‚¢‚ج‚إ•ھ‚©‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA“–ژپAƒCƒGƒX—l‚ج’يژq‚حپAڈ\“ٌژg“k‚ً•M“ھ‚ة•S“ٌڈ\گl‚خ‚©‚è‚ھƒGƒ‹ƒTƒŒƒ€‚ةڈW‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚¢‚¸‚ê‚ة‚¹‚وپA‚»‚ج’†‚ج“ٌگl‚إ‚ ‚ء‚½‚ةˆل‚¢‚ة‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
پ@“ٌگl‚ھŒü‚©‚ء‚ؤ‚¢‚½ƒGƒ}ƒI‚ئ‚¢‚¤‘؛‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAچ،“ْ‚ا‚±‚ة‚ ‚é‚ج‚©“ء’è‚·‚邱‚ئ‚ح‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپBƒGƒ‹ƒTƒŒƒ€‚©‚çکZڈ\ƒXƒ^ƒfƒBƒIƒ“‚خ‚©‚è—£‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ئڈ‘‚¢‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚؟‚ه‚ء‚ئ—]Œv‚بکb‚إ‚·‚ھپAƒIƒٹƒ“ƒsƒbƒN‚ج”ڈث‚ج’n‚إ‚ ‚éƒMƒٹƒVƒƒ‚جƒIƒٹƒ“ƒsƒA‚ج‹£‹Zڈê‚ة‚حپAƒXƒ^پ[ƒg‚©‚çƒSپ[ƒ‹‚ـ‚إ192.27ƒپپ[ƒgƒ‹‚ج’¼گü‘–کH‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚±‚ج‘–کH‚ًƒXƒ^ƒfƒBƒIƒ“‚ئŒ¾‚¢‚ـ‚µ‚ؤپAچ،‚جƒXƒ^ƒWƒAƒ€‚جŒêŒ¹‚إ‚à‚ ‚é‚»‚¤‚إ‚·پB‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إپAکZڈ\ƒXƒ^ƒfƒBƒIƒ“‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA192.27ƒپپ[ƒgƒ‹‚ًکZڈ\”{‚µ‚ـ‚·‚ئ11536.2ƒپپ[ƒgƒ‹پA–ٌڈ\“ٌƒLƒچپAژO—¢‚ج“¹‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB•à‚¢‚ؤ“ٌپAژOژٹش‚ئ‚¢‚¤‚ئ‚±‚ë‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@‘½•ھپA‚±‚ج“ٌگl‚حƒGƒ}ƒIڈoگg‚ج’يژq‚¾‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پA‚ئ‚¢‚¤گl‚ھ‚¢‚ـ‚·پBژ„‚à‚»‚ٌ‚ب‹C‚ھ‚·‚é‚ج‚إ‚·پB‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپAƒGƒ}ƒI‚ةŒü‚©‚¤“ٌگl‚ج’يژq‚جژp‚حپA‰½‚©‚ج–ع“I‚ةŒü‚©‚ء‚ؤ•à‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚و‚è‚àپA‘هگط‚ب–ع“I‚©‚ç—£‚ê‚ؤ‚¢‚‚و‚¤‚بپA‚»‚ٌ‚ب—ژ’_‚جژp‚ةŒ©‚¦‚é‚©‚ç‚إ‚·پBƒGƒ}ƒI‚ةŒü‚©‚¤‚ئ‚¢‚¤‚و‚è‚àپAƒGƒ‹ƒTƒŒƒ€‚ً—£‚ê‚ؤ‚¢‚“ٌگl‚ج’يژq‚ئŒ¾‚ء‚½•û‚ھپA“I‚ًژث‚½•\Œ»‚ب‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB—v‚·‚é‚ةپA‚±‚ê‚ح“s—ژ‚؟‚جکb‚ب‚ج‚إ‚·پBپ@ |
|
|
|
|
|
پ@‚»‚ٌ‚ب“ٌگl‚ج‚à‚ئ‚ةپA•œٹˆ‚جƒCƒGƒX—l‚ھ‹ك‚أ‚¢‚ؤ‚±‚ç‚êپA•à‚ف‚ً‹¤‚ة‚³‚ꂽ‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھپAچ،“ْ‚ج‚ئ‚±‚ë‚ةڈ‘‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@پu‚؟‚ه‚¤‚ا‚±‚ج“ْپA“ٌگl‚ج’يژq‚ھپAƒGƒ‹ƒTƒŒƒ€‚©‚çکZڈ\ƒXƒ^ƒfƒBƒIƒ“—£‚ꂽƒGƒ}ƒI‚ئ‚¢‚¤‘؛‚ضŒü‚©‚ء‚ؤ•à‚«‚ب‚ھ‚çپA‚±‚جˆêگط‚جڈo—ˆژ–‚ة‚آ‚¢‚ؤکb‚µچ‡‚ء‚ؤ‚¢‚½پBکb‚µچ‡‚¢ک_‚¶چ‡‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئپAƒCƒGƒXŒنژ©گg‚ھ‹ك‚أ‚¢‚ؤ—ˆ‚ؤپAˆêڈڈ‚ة•à‚«ژn‚ك‚ç‚ꂽپBپvپi13-15گكپj
پ@‚±‚±‚ة‚حپAˆê‚آ‚جŒb‚ف‚ھژ¦‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB”ق‚ç‚حƒCƒGƒX—l‚جژ€‚ةژ¸–]‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB—ژ’_‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBگS‚ة‹َ‚µ‚³‚ھ‚¢‚ء‚د‚¢ٹg‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ج‚و‚¤‚ب”ك‚µ‚ف‚ً‚à‚ء‚ؤپA”ق‚ç‚ح’يژq‚½‚؟‚جڈW’c‚ً—£‚êپAŒج‹½‚ة‹A‚낤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚·پB‚µ‚©‚µپA‚»‚ٌ‚ب“ٌگl‚جگS‚ج’†‚ة‚حپA‚؟‚ه‚¤‚اڈء‚¦‚©‚©‚ء‚½à•‰خ‚ج’†‚ة‚à‚ـ‚¾ڈ¬‚³‚ب‰خژي‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ‚ ‚é‚و‚¤‚ةپA‚ب‚¨ƒCƒGƒX—l‚ج‚±‚ئ‚ھ–Y‚ê‚ç‚ê‚ب‚¢‹Cژ‚؟‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB•à‚«‚ب‚ھ‚ç“ٌگl‚إکb‚·‚±‚ئ‚ئ‚¢‚¦‚خŒJ‚è•ش‚µƒCƒGƒX—l‚جکb‚خ‚©‚è‚إ‚ ‚ء‚½‚ج‚إ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚à‚ء‚ئ‚àپA‚»‚ê‚ح“ٌگl‚جگM‹آ‚ً”R‚¦—§‚½‚¹‚é‚و‚¤‚بŒi‹C‚ج‚¢‚¢کb‚إ‚ح‚ب‚پAڈء‚¦‚ؤ‚¢‚‰خ‚ًچإŒم‚جڈuٹش‚ـ‚إ–¼ژcگة‚µ‚ق‚و‚¤‚ب—ز‚µ‚¢کb‚¾‚ء‚½‚ةˆل‚¢‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
پ@ˆê‚آ‚جŒb‚ف‚ئگ\‚µ‚ـ‚µ‚½‚ج‚حپA‚½‚ئ‚¦‚»‚¤‚إ‚ ‚ء‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚àپAƒCƒGƒX—l‚ج‚±‚ئ‚ھŒê‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚±‚ë‚ةپAƒCƒGƒX—l‚ح‹ك‚أ‚¢‚ؤ‚«‚ؤ‚‚¾‚³‚èپA•à‚ف‚ً‹¤‚ة‚µ‚ب‚ھ‚çپA‚»‚جکb‚ً’ڑ”J‚ة’®‚«پA‚¢‚آ‚جٹش‚ة‚©ژه“±Œ ‚ًژه‚ھˆ¬‚ء‚ؤ‚‚¾‚³‚èپAڈء‚¦‚©‚©‚ء‚½‰خ‚ً‚à‚¤ˆê“xگشپX‚ئ”R‚¦—§‚½‚¹‚é‚و‚¤پAژه‚²ژ©گg‚ھ“±‚¢‚ؤ‚‚¾‚³‚é‚ج‚¾‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@ژ„’B‚à“¯‚¶‚و‚¤‚بŒb‚ف‚ًŒoŒ±‚·‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پBƒCƒGƒX—l‚ج‚±‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤکb‚·‚ئ‚«پA‚¢‚آ‚àگM‹آ‚ئٹى‚ر‚ةˆى‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚حŒہ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB–]‚ف‚ًژ¸‚ء‚ؤ‚¢‚½‚èپA‹^‚¢‚ة‚©‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½‚èپA‚¢‚ë‚¢‚ë‚بژ‚ھ‚ ‚é‚ج‚إ‚·پB‚»‚ê‚إ‚àپAƒCƒGƒX—l‚ج‚±‚ئ‚ھŒê‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ح‘هگط‚ب‚±‚ئ‚إ‚ ‚è‚ـ‚µ‚ؤپAƒCƒGƒX—l‚ح‚²ژ©•ھ‚ج‚±‚ئ‚ھکb‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éڈٹ‚ة•K‚¸—ˆ‚ؤ‚‚¾‚³‚èپA‚»‚جکb‚ً•·‚¢‚ؤ‚‚¾‚³‚é‚ج‚إ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚»‚µ‚ؤژ¶‚é‚إ‚à‚ب‚پA’Q‚‚إ‚à‚ب‚پA‹¤‚ة•à‚ف‚آ‚آپAژ„’B‚جژè‚©‚çژه“±Œ ‚ً—a‚©‚èژَ‚¯‚ؤ‚‚¾‚³‚èپA‚»‚جکb‚ً‹^‚¢‚©‚çگM‹آ‚ضپAژ¸–]‚©‚çٹَ–]‚ضپA”ك‚µ‚ف‚©‚çˆش‚ك‚ضپAٹى‚ر‚ضپA‚ئ“±‚¢‚ؤ‚‚¾‚³‚é‚ج‚إ‚ ‚è‚ـ‚·پB |
|
|
|
|
|
پ@‚ئ‚±‚ë‚ھپA‚»‚ج‚و‚¤‚بŒb‚ف‚ھپA“ٌگl‚ج—·کH‚ً•ï‚ٌ‚إ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ةپA”ق‚ç‚ح‚·‚®‚ة‚ح‚»‚ج‚±‚ئ‚ة‹C‚أ‚©‚ب‚©‚ء‚½‚ئپA‹L‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@پu‚µ‚©‚µپA“ٌگl‚ج–ع‚حژص‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ؤپAƒCƒGƒX‚¾‚ئ‚ح•ھ‚©‚ç‚ب‚©‚ء‚½پBپvپi16گكپj
پ@ƒ}ƒOƒ_ƒ‰‚جƒ}ƒٹƒA‚àپAژه‚ًŒ©‚½‚»‚جڈuٹش‚ة‚ح‚»‚ê‚ئ‚ح•ھ‚©‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پBژ„’B‚حŒ©‚ؤ‚¢‚ب‚ھ‚猩‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھ‚½‚‚³‚ٌ‚ ‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB‚ ‚é•û‚ھپAپu‹³‰ï‚ةچs‚‚ة—l‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚©‚çچs‚گوپX‚إپA‹³‰ï‚جڈ\ژڑ‰ث‚ھ–ع‚ة‚ئ‚ـ‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پv‚ئ‹آ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‹t‚ة‚¢‚¤‚ئپA‹»–،‚â•K—v‚ًٹ´‚¶‚ؤ‚¢‚ب‚¯‚ê‚خپA‚½‚ئ‚¦‚»‚ê‚ھ‘¶چف‚µ‚ؤ‚¢‚ؤ‚àپAژ„’B‚ج–ع‚ة“ü‚ç‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پB
پ@گ_‚جŒb‚ف‚à‚»‚¤‚إ‚·پBپwƒwƒuƒ‰ƒCگl‚ض‚جژèژ†پx11ڈح1گك‚ة‚حپAپuگM‹آ‚ئ‚حŒ©‚¦‚ب‚¢ژ–ژہ‚ًٹm”F‚·‚邱‚ئ‚إ‚·پv‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBگ_‚جŒb‚ف‚حپA‘¶چف‚µ‚ب‚¢‚ج‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپBŒ©‚¦‚ب‚¢ژ–ژہ‚ئ‚µ‚ؤ‘¶چف‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚ê‚ًژ„’B‚ةٹm”F‚³‚¹‚é“‚«‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھپAگM‹آ‚ب‚ج‚إ‚·پBگM‹آ‚ھ“‚‚ب‚ç‚خپA‚ا‚ٌ‚بˆأˆإ‚ج’†‚ً•à‚¢‚ؤ‚¢‚ؤ‚àگ_‚جŒb‚ف‚ًٹm”F‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپAگM‹آ‚ھ“‚¢‚ؤ‚¢‚ب‚¯‚ê‚خپA‚ا‚ٌ‚ب–¾‚邳‚ج’†‚ةگ¶‚«‚ؤ‚¢‚ؤ‚àپAگ_‚جŒb‚ف‚ًˆê‚آ‚à”F‚ك‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پB”F‚ك‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚¯‚ê‚خپA‚»‚ê‚ھژ„’B‚جگS‚ة‚¢‚©‚ب‚éٹى‚ر‚ً‚à‚½‚ç‚·‚±‚ئ‚à‚ب‚¯‚ê‚خپAٹ´ژس‚ً‚à‚½‚ç‚·‚±‚ئ‚à‚ب‚¢‚إ‚ ‚è‚ـ‚µ‚ه‚¤پB
پ@گ¹ڈ‘‚ة‚حپAپu“ٌگl‚ج–ع‚حژص‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½پv‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBژص‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA‰½‚©–W‚°‚ئ‚ب‚é‚à‚ج‚ھ–ع‚ج‘O‚ة’u‚©‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚è‚ـ‚µ‚ه‚¤پB
پ@‚µ‚©‚µپA‚à‚ئ‚à‚ئ‚جƒMƒٹƒVƒƒŒê‚جˆس–،‚ً’H‚ء‚ؤ‚ف‚ـ‚·‚ئپA‚»‚ê‚ئ‚ح‚؟‚ه‚ء‚ئƒjƒ…ƒAƒ“ƒX‚ھˆل‚¤‚ج‚إ‚·پBƒMƒٹƒVƒƒŒê‚جŒ¾—t‚إ‚حپAژè‚إ’ح‚قپAژ‚آپAژx”z‚·‚éپA•غ‚آ‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBŒˆ‚µ‚ؤˆ«‚¢ˆس–،‚¾‚¯‚ةژg‚ي‚ê‚é‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚‚ؤپBƒCƒGƒX—l‚ھڈڈ—‚جژè‚ًژو‚ء‚ؤپuƒ^ƒٹƒ^پEƒNƒ€پiڈڈ—‚وپA‹N‚«‚ب‚³‚¢پjپv‚ئŒ¾‚ي‚ꂽپA‚»‚جژ‚ةپuژè‚ًژو‚éپv‚ئ‚¢‚¤•—‚ةژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚錾—t‚àپA‚±‚جŒ¾—t‚ب‚ج‚إ‚·(ƒ}ƒ‹ƒR5:41)پB‚ ‚é‚¢‚حپwƒwƒuƒ‰ƒCگl‚ض‚جژèژ†پx‚ج’†‚إپAپuژ„‚½‚؟‚جچگ”’‚·‚éگM‹آ‚ً‚µ‚ء‚©‚è•غ‚ئ‚¤‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پv‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپA‚»‚ج’†‚إپuگM‹آ‚ً•غ‚آپv‚ئ‚¢‚¤‚س‚¤‚ةژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚錾—t‚àپA‚±‚جŒ¾—t‚ب‚ج‚إ‚·پiƒwƒuƒ‹4:14پjپB‹t‚ةپAژص‚é‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚بˆس–،‚إژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚±‚±‚¾‚¯‚¾‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚à‚¢‚¢‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB
پ@‚»‚¤‚·‚é‚ئپA‚±‚±‚إ–ع‚ھژص‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپAژ©•ھ‚جٹO‚ة‰½‚©–W‚°‚ئ‚ب‚éڈلٹQ•¨‚ھ’u‚©‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚و‚è‚àپAژ©•ھژ©گg‚ھ“à‚ةژ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚à‚جپA•غ‚؟‘±‚¯‚ؤ‚¢‚é‚à‚جپA‚µ‚ء‚©‚è’ح‚ٌ‚إ—£‚¹‚ب‚¢‚إ‚¢‚é‚à‚ج‚ھپAچ،–ع‚ج‘O‚ةŒ»‚ê‚ؤ‚‚¾‚³‚ء‚ؤ‚¢‚é•œٹˆ‚جژهƒCƒGƒX‚ً”F‚ك‚³‚¹‚ب‚¢‚و‚¤‚ة“‚¢‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚é‚ج‚إ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@‚»‚ج‚و‚¤‚ة–ع‚ج‘O‚ة‚¢‚ç‚ء‚µ‚ل‚éƒCƒGƒX—l‚ھ”F‚ك‚ç‚ê‚ب‚¢‚ظ‚ا‚ةپA”ق‚ç‚جگS‚ً”›‚ء‚ؤ—£‚³‚ب‚©‚ء‚½‚à‚ج‚ئ‚ح‚¢‚ء‚½‚¢‰½‚إ‚ ‚è‚ـ‚µ‚ه‚¤‚©پB‚»‚ê‚ح”ق‚ç‚ھ“¹پXکb‚µ‘±‚¯‚ؤ‚«‚½“ٌ‚آ‚ج‚±‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤژ¦‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBˆê‚آ‚حڈ\ژڑ‰ث‚إژ€‚ب‚ꂽƒCƒGƒX—l‚ج‚±‚ئپA‚à‚¤ˆê‚آ‚ح‹َ‚ء‚غ‚¾‚ء‚½ƒCƒGƒX—l‚ج‚¨•و‚ج‚±‚ئ‚إ‚·پBڈ\ژڑ‰ث‚جژ€‚حپA”ق‚ç‚ھ–]‚ف‚ً‚©‚¯‚ؤ‚¢‚½ƒCƒGƒX—l‚ئ‚جŒً‚ي‚è‚ھ‰i‰“‚ة’f‚½‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚±‚ئ‚ًˆس–،‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‹َ‚ء‚غ‚ج‚¨•و‚حپA”ق‚ç‚ھƒCƒGƒX—l‚ئ‹¤‚ةگ¶‚«‚ؤ‚«‚½‚±‚ئ‚جژv‚¢ڈo‚âڈط‚µ‚ھ‹َ‚µ‚ڈء‚¦‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚±‚ئ‚ًˆس–،‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚±‚ê‚ç“ٌ‚آ‚ج‚±‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤپA”ق‚ç‚جگS‚حƒCƒGƒX—l‚ئ‹¤‚ة‚ ‚ء‚½گ¢ٹE‚ًژ¸‚¢پAƒCƒGƒX—l‚ج‚¢‚ب‚¢ˆأچ•‚جگ¢ٹE‚ة–ہ‚¢چ‚ٌ‚إ‚µ‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚·پB
پ@ژ„‚حپA17-18گك‚ةژ¦‚³‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھپA‚±‚ج‚و‚¤‚ب“ٌگl‚جگSڈî‚ً‚و‚•¨Œê‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
پ@پuƒCƒGƒX‚حپAپw•à‚«‚ب‚ھ‚çپA‚â‚èژو‚肵‚ؤ‚¢‚é‚»‚جکb‚ح‰½‚ج‚±‚ئ‚إ‚·‚©پx‚ئŒ¾‚ي‚ꂽپB“ٌگl‚حˆأ‚¢ٹç‚ً‚µ‚ؤ—§‚؟ژ~‚ـ‚ء‚½پB‚»‚جˆêگl‚جƒNƒŒƒIƒp‚ئ‚¢‚¤گl‚ھ“ڑ‚¦‚½پBپwƒGƒ‹ƒTƒŒƒ€‚ة‘طچف‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚ھ‚çپA‚±‚جگ”“ْ‚»‚±‚إ‹N‚±‚ء‚½‚±‚ئ‚ًپA‚ ‚ب‚½‚¾‚¯‚ح‚²‘¶‚¶‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚©پBپxپv(17-18گك)
پ@•œٹˆ‚جژه‚ھ‹¤‚ة•à‚¢‚ؤ‚‚¾‚³‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ةپA“ٌگl‚ح‚ـ‚ء‚½‚ˆأ‚¢ٹç‚ً‚µ‚ؤپA‚µ‚©‚à”ٌ“ï‚ھ‚ـ‚µ‚ƒCƒGƒX—l‚ة‚±‚¤Œ¾‚¢•ْ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپu‚±‚جگ”“ْ‚ة‹N‚±‚ء‚½‚ ‚جڈo—ˆژ–‚ًپA‚ ‚ج‘ه”كŒ€‚ًپA‚ ‚ب‚½‚¾‚¯‚ح‰½‚à’m‚ç‚ب‚¢‚ج‚إ‚¢‚½‚ج‚إ‚·‚©پv‚ئپBژ„’B‚àپA“¯‚¶‚±‚ئ‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پBژ„‚½‚؟‚ھ‚±‚ٌ‚ب‹ê‚µ‚ٌ‚إ‚¢‚é‚ج‚ةپA‚ ‚ب‚½‚¾‚¯‚ح’m‚ç‚تٹç‚ج”¼•؛‰q‚ب‚ج‚إ‚·‚©پBگ¢ٹE‚جŒ»ژہ‚ھ‚±‚ٌ‚ب‚ة‚à”كژS‚إ‚ ‚é‚ج‚ةپA‚ ‚ب‚½‚¾‚¯‚ح•تگ¢ٹE‚ب‚ج‚إ‚·‚©پB‰“‚پAچ‚‚«‚ئ‚±‚ë‚ة‚¨‚ç‚ê‚ؤپAژ„’B‚جگ¢ٹE‚جŒ»ژہ‚ة‰½‚جٹض‚ي‚è‚àژ‚ئ‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚ç‚ب‚¢‚ج‚إ‚·‚©پBپu‚ ‚ب‚½‚¾‚¯‚حپv‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚حپA‚à‚ح‚âƒCƒGƒX—l‚ئ‹¤‚ة‚¢‚ؤ‚‚¾‚³‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ًگM‚¶‚ؤ‚¢‚ب‚¢گS‚جڈَ‘ش‚ً•\‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·پB
پ@‚±‚ج‚و‚¤‚بگS‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپAگو’ِ—ˆگ\‚µڈم‚°‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚و‚¤‚ةپAƒCƒGƒX—l‚ھژ„’B‚جŒ»ژہ‚ً’m‚ء‚ؤ‚‚¾‚³‚ç‚ب‚¢‚ج‚إ‚ح‚ب‚پAژ„’B‚ج•û‚إƒCƒGƒX—l‚ھگ¶‚«‚ؤ‚¨‚ç‚ê‚é‚ئ‚¢‚¤Œ»ژہ‚ًٹو‚ب‚ة”غ‚ٌ‚إ‚µ‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚錋‰ت‚ب‚ج‚إ‚·پB‹َ‚ء‚غ‚ج•و‚ةŒ»‚ꂽ“Vژg‚حپA•wگl‚½‚؟‚ة‚±‚ج‚و‚¤‚ةŒ¾‚¢‚ـ‚µ‚½پBپu‚ب‚ٌ‚¼ژ€‚ة‚µژز‚ا‚à‚ج’†‚ةگ¶‚¯‚éژز‚ًگq‚ت‚é‚©پvپB‚ا‚¤‚¹ƒCƒGƒX—l‚ب‚ٌ‚©‚¢‚ب‚¢‚ج‚¾پB‚ا‚¤‚¹ƒCƒGƒX—l‚ح‰½‚à‚µ‚ؤ‚‚ê‚ب‚¢‚ج‚¾پB‚»‚ٌ‚ب•—‚ةپAگ¶‚¯‚éژهچف‚ًپAژ€‚ة‚µژز‚ج‚²‚ئ‚‹َ‚µ‚¢‚à‚جپA–³—ح‚ب‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤŒˆ‚ك‚آ‚¯‚邱‚ئ‚ً‚µ‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پBپu”ق‚ح‚±‚±‚ةچفپi‚¢‚ـپj‚³‚¸پAلS‚è‹‹‚¦‚èپv‚ئپA“Vژg‚حچگ‚°‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·پBژه‚حگ¶‚«‚ؤ‚¨‚ç‚ê‚é‚ئ‚¢‚¤گM‹آ‚ب‚‚µ‚ؤپAژه‚ھگ¶‚«‚ؤ‚¨‚ç‚ê‚錻ژہ‚حŒ©‚¦‚ؤ—ˆ‚ـ‚¹‚ٌپB |
|
|
|
|
|
پ@ƒGƒ}ƒI‚ةŒü‚©‚¤“ٌگl‚ج’يژq‚ج•¨Œê‚حپA‚»‚ج‚و‚¤‚ةگ_‚ب‚«–]‚ف‚ب‚«گ¢ٹE‚ة–ہ‚¢چ‚ٌ‚إ‚µ‚ـ‚ء‚½“ٌگl‚جچ°‚ھپAƒCƒGƒX—l‚جŒb‚فگ[‚¢“±‚«‚ة‚و‚è‚ـ‚µ‚ؤپAچؤ‚رگ_‚ج‚¢‚ـ‚·گ¢ٹE‚ةکA‚ê–ك‚³‚ꂽ‚ئ‚¢‚¤•¨Œê‚ب‚ج‚إ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚¢‚©‚ة‚µ‚ؤپAژه‚ح‚±‚ج“ٌگl‚ج—ژ’_‚ئ–ہ‚¢‚ج’†‚ة‚ ‚éچ°‚ً“±‚«پAژو‚è–ك‚³‚ꂽ‚ج‚©پBچ،“ْ‚حژٹش‚ھ‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ج‚إپAژں‰ٌ‚ـ‚½‚±‚ج‘±‚«‚ً’ڑ”J‚ة‚¨کb‚µ‚µ‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
پ@‚½‚¾پAچإŒم‚ج•”•ھ‚¾‚¯ٹm”F‚µ‚ؤ‚¨‚«‚ـ‚µ‚ه‚¤پB
پ@پuˆêچs‚ح–عژw‚·‘؛‚ة‹ك‚أ‚¢‚½‚ھپAƒCƒGƒX‚ح‚ب‚¨‚àگو‚ضچs‚±‚¤‚ئ‚³‚ê‚é—lژq‚¾‚ء‚½پB“ٌگl‚ھپAپwˆêڈڈ‚ة‚¨”‘‚ـ‚è‚‚¾‚³‚¢پB‚»‚ë‚»‚ë—[•û‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚µپA‚à‚¤“ْ‚àŒX‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚©‚çپx‚ئŒ¾‚ء‚ؤپA–³—‚ةˆّ‚«ژ~‚ك‚½‚ج‚إپAƒCƒGƒX‚ح‹¤‚ة”‘‚ـ‚邽‚ك‰ئ‚ة“ü‚ç‚ꂽپBˆêڈڈ‚ةگHژ–‚جگب‚ة’…‚¢‚½‚ئ‚«پAƒCƒGƒX‚حƒpƒ“‚ًژو‚èپAژ^”ü‚ج‹F‚è‚ًڈ¥‚¦پAƒpƒ“‚ً—ô‚¢‚ؤ‚¨“n‚µ‚ة‚ب‚ء‚½پB‚·‚é‚ئپA“ٌگl‚ج–ع‚ھٹJ‚¯پAƒCƒGƒX‚¾‚ئ•ھ‚©‚ء‚½‚ھپA‚»‚جژp‚حŒ©‚¦‚ب‚‚ب‚ء‚½پBپv(28-31گك)
پ@—[•é‚êپAƒGƒ}ƒI‚ة’…‚¢‚½’يژq‚½‚؟‚حپA“r’†‚©‚瓹کA‚ê‚ئ‚ب‚ء‚½‚±‚ج•sژv‹c‚بŒن•û‚ةپAپu‚ا‚¤‚¼پA‚²ˆêڈڈ‚ة‚¨”‘‚ـ‚è‚‚¾‚³‚¢پv‚ئ‹‚¢‚ؤ‚¨ٹè‚¢‚ً‚µ‚½‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپu‚ ‚ب‚½‚¾‚¯‚ح‰½‚à‚µ‚ç‚ب‚¢‚ج‚إ‚·‚©پv‚ئپAƒCƒGƒX—l‚ً‰ل’ ‚جٹO‚جگlٹش‚ئ‚µ‚ؤ“ث‚«•ْ‚µ‚ؤ‚¢‚邤‚؟‚حپA‚½‚ئ‚¦‚ا‚ٌ‚ب‚ة‹ك‚‚ةژه‚ھ‚¨‚ç‚ê‚ؤ‚àپAŒˆ‚µ‚ؤ‚»‚ج‘¶چف‚ة‹C‚أ‚‚±‚ئ‚ح‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB‚µ‚©‚µپAژه‚جˆ¤‚ئ“±‚«‚حپA‚±‚ج“ٌگl‚جٹو‚بگS‚ً‘إ‚؟چس‚¢‚ؤپAپu‚ا‚¤‚¼ژه‚وپA—ˆ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB‚¨ڈh‚è‚‚¾‚³‚¢پv‚ئ‹F‚éژز‚ة•د‚¦‚ؤ‚‚¾‚³‚ء‚½‚ج‚إ‚µ‚½پB
پ@‚»‚µ‚ؤپA•œٹˆ‚ج“ْ‚ج’©پAƒ}ƒOƒ_ƒ‰‚جƒ}ƒٹƒA‚ھ•œٹˆ‚جژه‚ة‚ـ‚ف‚¦‚½‚و‚¤‚ةپA‚»‚ج—[‚ׂةپA‚±‚ج“ٌگl‚ج’يژq‚à‚ـ‚½•œٹˆ‚جژه‚ة‚ـ‚ف‚¦‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚½‚ج‚إ‚·پB‚±‚ج‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚ًٹo‚¦‚ؤپAژ„’B‚حژه‚ةڈo‰ï‚¤“ْ‚ئ‚µ‚ؤپA“ْ—j“ْ‚ج’©‚ةپA—[‚ׂةپA—ç”q‚ًژç‚葱‚¯‚éژز‚إ‚ ‚肽‚¢‚ئٹè‚¢‚ـ‚·پBپ@ |
|
|
|

|
|
| گ¹ڈ‘پ@گV‹¤“¯–َپF |
(c)‹¤“¯–َگ¹ڈ‘ژہچsˆدˆُ‰ï
Executive Committee of The Common Bible
Translation
(c)“ْ–{گ¹ڈ‘‹¦‰ï
Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
|
|
|