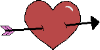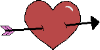|
|
|
|
明治時代を代表する文学者に、正岡子規がいます。七年間結核を患い、三十四歳で亡くなりました。晩年にはカリエスも発症します。カリエスは、結核菌に骨がおかされ、骨が腐り破壊されるたいへん恐ろしい病気です。激しい苦痛のために、子規は歩くことも困難となり、次第に寝込むことが多くなり、ついにはまったくの寝たきりになってしまいました。そのような病苦の中で、子規は、鎮痛剤で苦痛を和らげながら死ぬまで創作活動を続け、後進の指導を続けたのでした。
子規が晩年に書いたものに『墨汁一滴』という随筆があります。新聞「日本」に明治34年から164回にわたって連載したものです。喀血をしながら、苦痛に耐えながら書いたものと思われますが、そういうことを思わせない軽やかな文体が不思議です。その中に、今日まずご紹介したい文章があるのです。
散歩の楽、旅行の楽、能楽演劇を見る楽、寄席に行く楽、見せ物興行物を見る楽、展覧会を見る楽、花見月見雪見等に行く楽、細君を携へて湯治に行く楽、紅燈(こうとう)緑酒(りょくしゅ)美人の膝を枕にする楽、目黒の茶屋に俳句会を催して栗飯の腹を鼓する楽、道灌山に武蔵野の広きを眺めて崖端(がけはな)の茶店に柿をかじる楽。歩行の自由、坐臥の自由、寐返りの自由、足を伸す自由、人を訪ふ自由、集会に臨む自由、厠に行く自由、書籍を捜索する自由、癇癪の起りし時腹いせに外へ出て行く自由、ヤレ火事ヤレ地震といふ時に早速飛び出す自由。――総ての楽、総ての自由は尽く余の身より奪ひ去られて僅かに残る一つの楽と一つの自由、即ち飲食の楽と執筆の自由なり。しかも今や局部の疼痛劇しくして執筆の自由は殆ど奪はれ、腸胃漸(ようや)く衰弱して飲食の楽またその過半を奪はれぬ。アア何を楽に残る月日を送るべきか。
耶蘇信者某一日余の枕辺に来り説いて曰くこの世は短いです、次の世は永いです、あなたはキリストのおよみ返りを信ずる事によつて幸福でありますと。余は某の好意に対して深く感謝の意を表する者なれども、奈何(いかん)せん余が現在の苦痛余り劇しくしていまだ永遠の幸福を謀るに暇(いとま)あらず。願くは神先づ余に一日の間(ひま)を与へて二十四時の間(あいだ)自由に身を動かしたらふく食を貪らしめよ。而して後に徐(おもむ)ろに永遠の幸福を考へ見んか。(正岡子規、『墨汁一滴』)
クリスチャンの友人が、子規を見舞いにきました。そして、イエス様の話をしたり、永遠の命の話をしたりして、子規を慰め、励まそうとします。しかし子規は、「永遠の幸福」も有り難い話だとは思うけれども、現在の我が身はそれどころじゃない。絶え間ない苦痛と闘っていて、そんなことをゆっくり考えているゆとりがないのだ。わたしを救ってくださる神さまがおられるというなら、まず24時間でいいから、わたしをこの絶え間ない苦痛から解放して欲しい。そうすれば永遠の幸福というものを考える心のゆとりもできるだろうと言っているのです。
クリスチャンとしては、すんなりと「そうですね」といえないような話かもしれません。けれども、子規の言わんとすることはわかる。というよりも、本当にその通りだとさえ思うのです。痛みに泣いたり、喚いたり、叫んでいるときに、あるいは恐れや不安、悲しみや絶望の中に座り込んでしまっているときに、やれ永遠の命だ、やれ終末だ、天国だという話をされても、そういうことに頭が回らない。気持ちがついていけない。それよりも今の現実をなんとかしてくれということになるのではないでしょうか。
わたしは、子規は人間として当たり前のことを言っていると思うのです。逆に、こういう人に対して「あなたはよほど心が頑な人です。」などとうそぶくクリスチャンがいるとしたら、そのほうがよほど的はずれな言い分だと言いたいと思います。
イエス様は、どのように神様の愛と救いを人々にお伝えになったでしょうか? 病める人々には、まずその病を癒され、友なき者には、まず友となり、飢えている人には、まずパンをお与えになり、嵐になやむ者には、その嵐をお鎮めになったのではありませんでしょうか。それから「恐れるな。あなたの罪はゆるされた。神さまはあなたと共におられる。神様の愛と救いの力を信じなさい。永遠の命を信じなさい」と仰ったのではありませんでしょうか。イエスさまは、「信じなさい」、「求めなさい」というだけではなく、信じることも求めることも儘ならぬような人間に近づき、その力を与えてくださったのです。
例をあげれば切りがありませんが、たとえば、ゲラサという地方にレギオンという悪霊に取り憑かれ、正気を失っていた男がいました。聖書にはこう書かれています。
イエスが舟から上がられるとすぐに、汚れた霊に取りつかれた人が墓場からやって来た。この人は墓場を住まいとしており、もはやだれも、鎖を用いてさえつなぎとめておくことはできなかった。これまでにも度々足枷や鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり足枷は砕いてしまい、だれも彼を縛っておくことはできなかったのである。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ちたたいたりしていた。イエスを遠くから見ると、走り寄ってひれ伏し、大声で叫んだ。「いと高き神の子イエス、かまわないでくれ。後生だから、苦しめないでほしい。」(『マルコによる福音書』5章1〜7節)
この男の人は、イエスさまに「わたしにかまわないでくれ。」というのです。「かまわないでくれ」というのは何の関わりも持とうとしないということです。しかし、イエスさまは「はい、そうですか」とはいいません。取り憑いたレギオンを男から追い出し、男の正気を取り戻してやるのです。ゲラサの人々は、今まで手のつけられなかった暴れ者が、イエス様の前に静かに座っているのをみて驚きます。
彼らはイエスのところに来ると、レギオンに取りつかれていた人が服を着、正気になって座っているのを見て、恐ろしくなった。
イエスさまの目から見たら、神様の愛を信じない人間は、皆正気を失っているのかもしれません。正気を失っていますから、何を言ってもまともには通じません。考えることも、話すことも、異常なのです。「豚に真珠」という諺は、実はイエス様のお言葉が出典です。イエス様は、豚に真珠を与えても、豚はそれを足で踏みにじり、向き直って噛みついてくるだけだと仰いました。正気を失った人間に、いくら神様の愛や救いを説いても同じ事が起こるのです。しかし、だからダメだというのではなく、イエス様はまず癒されるのです。正気を失った人間の正気を取り戻されるのです。そうすれば、イエス様のお話も、素直に分かるようになるのです。
これはレギオンに取り憑かれた男だけの話ではなく、イエス様と出会った人たちみんなそうなのです。もちろん、いろいろなケースがあります。だけど突き詰めてみると、自分の力でイエス様を信じた人はいません。「目からうろこ」、これもまた聖書からとられた諺です。パウロという人は、キリスト教徒が恐れるキリスト教迫害の急先鋒でありました。しかし、イエス様に出逢い、目から鱗のようなものが落ちて、180度、生き方が変わり、キリスト教伝道の使者となりました。パウロもまた正気を失っていた人間のひとりだったのです。しかも、少しも自分は極めてまともで、クリスチャンの方が異常だと信じ切っていたのです。しかし、イエス様によって彼は正気を取り戻し、本当の神様の愛と救いが分かったのでした。
そういうことからしますと、正岡子規が、「願くは神先づ余に一日の間(ひま)を与へて二十四時の間(あいだ)自由に身を動かしたらふく食を貪らしめよ。而して後に徐(おもむ)ろに永遠の幸福を考へ見んか。」というのは、実に的を射た話だといえるのではないでしょうか。私たちは子規にこう言えばいいのです。「その通りです。イエス様はそのように救いを与えてくださる御方です。では、まずそれを神様に祈り求めましょう」
誤解のないように付け加えておきますと、イエス様が必ず病を癒してくださると言っているのではありません。病の癒しが救いだと言っているのでもありません。しかし、私たちの求めるところを率直に求めるならば、神様はかならずそれに答えてくださる御方なのです。神様は答えてくださる、そこから信じ始め、また祈り始めればよいのであります。
|
|
|
|
|
|
今日は『ヘブライ人への手紙』11章5-7節をお読みしました。先週もお話ししましたように、この11章は、旧約聖書に登場する幾人かの信仰者の姿を示し、信仰とはこういうものであるということを、実際的に思い起こさせようとして書かれているところであります。先週はアベルのお話ししましたが、今日はエノクという信仰者について書かれていました。
聖書は、エノクについて多くのことを語っていません。最初に出てくるのが、今日ごいっしょに読んだ『創世記』5章のアダムの系図の中であります。アダムとエバは楽園を追放された後、カインとアベルを生みました。しかし、カインがアベルを殺してしまって、カインはその罪で追放されてしまいます。こうしてアダムとエバは、カインとアベルを一遍に失うことになるのですが、その後でセトという子をもうけます。その子孫の中にエノクが登場するのです。エノクはイエレドの息子で、メトシェラをはじめ数人の息子や娘をもうけた後、365歳で死んだということが書かれております。365歳というのはびっくりするほど長生きですが、系図の中の他の人たちに比べると短い。だいたい半分以下です。そういう意味では短命だったといってもいいのかもしれません。
さらにこう付け加えられています。
エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなった。
エノクは死んだのではなく、《神が取られたのでいなくなった》と言われています。これはどういうことなのか、後でお話しすることにしましょう。
次にエノクについて知ることができるのは、今日お読みしました『ヘブライ人への手紙』で、この『創世記』の記述を少し膨らませて、こう記していました。
信仰によって、エノクは死を経験しないように、天に移されました。神が彼を移されたので、見えなくなったのです。移される前に、神に喜ばれていたことが証明されていたからです。
さらにもう一箇所、『ユダの手紙』の中にエノクの話が出て来ます。
アダムから数えて七代目に当たるエノクも、彼らについてこう預言しました。「見よ、主は数知れない聖なる者たちを引き連れて来られる。それは、すべての人を裁くため、また不信心な生き方をした者たちのすべての不信心な行い、および、不信心な罪人が主に対して口にしたすべての暴言について皆を責めるためである。」(『ユダの手紙』1章14節)
これによりますと、アダムから七世代を数えるエノクの時代には、だいぶ神様の目に悪とみられることをする人が増えていたようです。エノクからさらに三代目に、ノアが生まれます。その頃には、神様がもう我慢ならいほど地上に悪が満ちていたというのですから、エノクの時代にはその予兆があらわれていてもおかしくありません。そういう人たちの中で、エノクは神様と共に歩む人であって、神を神としないような生き方をしている人々に対して、エノクは警告を発していたのだと言われているのです。ただし、エノクがこのような預言活動をしていたという記録は、旧約聖書の中にはありません。きっと聖書以外の言い伝えのなかにそういう話があったのでありましょう。
このようにエノクという信仰者について、わたしたちは、ほとんど話らしい話を知ることができないのですが、「エノクは神様と共に歩んだ」ということ、そのことについて今日は学びたいと思います。
「神様と共に歩む」というのは、どういうことなのでしょうか。もし神様が目に見えるお方であるならば、「神様と共の歩みたい」と思ったときにどうするか。神様についていけばいいのです。しかし、神様は見えません。そうしたらどうすればいいのか。『ヘブライ人への手紙』はこう書いています。
神に近づく者は、神が存在しておられること、また、神は御自分を求める者たちに報いてくださる方であることを、信じていなければならないからです。(11章6節)
見えない神様と共に歩むためには、二つのことが必要であると言われておりまして、まず神様の存在を信じることだ、と言っています。しかし、存在を信じているだけでは、神様と共に歩む、生きる、ということにはなりません。神様が私たちに答えてくださる御方である、ということを信じて生きなさいというです。それが《神は御自分を求める者たちに報いてくださる方であることを、信じていなければならない》と言われていることです。信仰とは「神様がいるか、いないか」、「神様がどんな性質の御方か」、そういう知識を身につけることではなく、神様と共に生きることです。そして、神様と共に生きるということは、神様が答えてくださるということを信じて、神様に求めることだと言われているのです
。
『マタイによる福音書』の中に、「カナンの女の信仰」というお話しがあります。カナン人の女性が娘の病を癒してくださいと、イエス様のところにやって訴えます。しかし、イエス様はそれをずっと無視なさっているのです。それでもこの女性は諦めることなくイエス様に訴え続けました。するとイエス様はこの女性に「わたしは神様からユダヤ人に福音を伝えるように遣わされたのだ。外国人であるあなたにではない。」と突き放しました。それでもこの女性は諦めなかった。「主よ、どうかお助け下さい」と泣き、わめき、さけび続けた。しかし、イエス様は、どうしてこんなに冷たいのかと思うのですが、「子どもたちのパンを小犬にやってはいけない」と言い放ちます。すると彼女は言いました。「しかし、小犬も主人の食卓から落ちるパン屑はいただきます」これを聞いてイエス様は、ようやくいつもイエス様に戻りまして、「婦人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りなるように」と仰ってくださったというのです。今日は、イエス様の冷たい態度の意味については不問に伏しておきましょう。ただひとつ確認したいのは、イエス様が立派だと誉められたカナン人の女性の信仰とは、必ず答えてくださると信じて求め続けたことだったということです。
エノクは神と共に歩んだというのは、決して神様が感心するような立派な生き方をしたという意味ではありません。ただ、神は必ず答えてくださるということを信じて生きたのです。そのことが、神様の喜びとされた。聖書にはそのように記されています。
|
|
|
|
|
|
ところで、先ほどお読みしました『創世記』5章ですが、そこには、アダムからのノアにいたるまでの系図が書かれています。そして「〜年生き、そして死んだ」という言葉が繰り返されていました。言うまでもないことですが、人は生きて死にます。どんな生き方をしても、結局はみんな同じように死ぬ。それが人生なのです。
そうすると、人生にはいったいどんな意味があるのかということも考えたくなります。どうせ死ぬんだったら、楽しく生きた方がいい。人に気を遣ったり、善悪の道徳に縛られたり、そんなことをやめて存分にやりたいことをして生きればいいではないか。そういう考えも起こりましょう。だけど、生きるということは楽しみばかりではなく、いろいろな苦しみが伴うものです。そうすると今度は、苦しみに耐えて生きるなら、はやく死んでしまった方がいいという考えも起こってきましょう。人生は思い通りにならないばかりか、必ず死ぬということが、生きるということに迷いを生じさせるのです。
この迷いを断ち切るには、私たちは死んでも生きる、ということを信じるしかないだろうと思います。人生は、ともすると無意味に思えてしまうことがある。しかし、人生の意味は、死んでから与えられる。神様が、わたしたちの生きてきた人生に意味と価値を与えてくださるのです。
聖書には、死ななかった人間がふたり登場します。逆に言うと、他の人たちはどんな立派な信仰であろうと、みんな死にました。そして、イエス様も死を経験されたのです。死ぬということは、私たちに与えられた神様の定めなのです。しかし、神様は敢えてエノクと預言者エリヤ、この二人には死を経験させることなく、天に召しになりました。
エノクの場合、彼は死んだのではなく、「神が取られたので見えなくなった」、あるいは「神が死を経験しないように天に移された」ということが記されていました。いったい、なぜ、神様はこの二人にそのような特別なことをなさったのでしょうか。もちろん、神様のなさることですから、本当のところはわかりません。しかし、それを見た人たちは、この世から移り住む場所があるということを知ったでありましょう。人間の命は、決して死で終わるものではないということを、生きながら天に召されたエノクやエリヤは証ししていたのであります。
正岡子規は、死んだあとのことなど考えている余裕がないと申しました。この子規の生き様について、実はもっと話したいことがあります。子規は、最後まで死後の世界に望みをかけるということはしませんでした。あくまでも自分の命を生きるということに徹底した人でした。とても強い人です。つまるところ、ニーチェのいうところの「超人」だったのです。
これについては次週、もう少し丁寧にお話しをさせていただきたいと思います。私たちはニヒリズムに生きようとしているわけではありません。神を信じ、神が私の生に答えてくださる事を信じて生きるのです。立派に、強く生きられなくとも、神様に対して顔を上げ、神様に対して祈りつつ、歩み続ける者でありたいと願うのです。それが神と共に生きるということです。神様が喜び賜うことだと、聖書は私たちに教えてくれているのです。 |
|
 |
| 目次 |
|

|
|
| 聖書 新共同訳: |
(c)共同訳聖書実行委員会
Executive Committee of The Common Bible
Translation
(c)日本聖書協会
Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
|
|
|