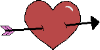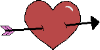|
|
|
|
私たちの人生には、起こるはずがない、起こってはならない、と思うことが、我が身のこととして起こることがあります。もっとも恐れていたことが、現実となってしまうのであります。
明治時代のキリスト者で、多くの人に影響を与えた内村鑑三と言う人がいます。内村鑑三には、ルツ子という愛娘がおりました。ルツ子は、いろいろな意味で、内村鑑三の心を支える娘で、彼は、彼女に格別なる愛を注いでおりました。しかし、ルツ子は、実践女学校を卒業したばかりの、17歳という若さで病死してしまったのです。ルツ子の死は、内村鑑三にとって、人生にあってはならないことの一つでありました。
たとえ日本を代表する優れたキリスト教指導者でありましても、愛娘を失う悲しみは、一人の子煩悩な父親の悲しみと少しも変わりありません。内村鑑三は、その打撃の大きさを、「神の手、余輩に加はりて、余輩の腿のつがい挫け、余輩はあゆむことを能はざるに至れり」と語っています。「腿のつがい挫け」とは、ヤボクの渡しで、神様と組み討ちしたヤコブと自分を重ねているのでしょう。ヤコブは、「祝福してくださらなければ、あなたを去らせません」と言って、神と格闘したと、聖書に記されています。その時、ヤコブは、腿のつがいを負傷したのです。内村鑑三も、愛娘の癒しを願い、ヤコブのように、神に挑む祈りを捧げてきたのでありましょう。しかし、あえなく死んでしまった。それを、「腿のつがい挫け」と表現しているのです。
しかし、腿のつがいが挫けるというヤコブの話を読んでみますと、意外なことが書いてあります。ちょっと聖書を読んでみましょう。
その夜、ヤコブは起きて、二人の妻と二人の側女、それに十一人の子供を連れてヤボクの渡しを渡った。皆を導いて川を渡らせ、持ち物も渡してしまうと、ヤコブは独り後に残った。そのとき、何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところが、その人はヤコブに勝てないとみて、ヤコブの腿の関節を打ったので、格闘をしているうちに腿の関節がはずれた。もう去らせてくれ。夜が明けてしまうから」とその人は言ったが、ヤコブは答えた。「いいえ、祝福してくださるまでは離しません。」(『創世記』32章23〜27節)
《その人はヤコブに勝てないとみて、ヤコブの腿の関節を打ったので、格闘しているうちに腿の間接がはずれた》、つまり勝てないと思ったのは、ヤコブではなく、神の人の方であったというのです。さらに読み進めていきますと、
「お前の名は何というのか」とその人が尋ね、「ヤコブです」と答えると、その人は言った。「お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と闘って勝ったからだ。」「どうか、あなたのお名前を教えてください」とヤコブが尋ねると、「どうして、わたしの名を尋ねるのか」と言って、ヤコブをその場で祝福した。(29-30節)
神の人は、はっきりと「お前は神に勝った」と言っています。そして、ヤコブは神の祝福を得たのです。しかし、その代償として、腿のつがいを負傷したのでした。
ヤコブがペヌエルを過ぎたとき、太陽は彼の上に昇った。ヤコブは腿を痛めて足を引きずっていた。(32節)
ヤコブはこの日より自分の足を引きずりながら、神の祝福の道を歩むことになりました。他方、内村鑑三は、「神の手、余輩に加はりて、余輩の腿のつがい挫け、余輩はあゆむことを能はざるに至れり」と言っています。もう、歩くことができなくなったというのです。しかし、実際は、この後も彼はキリスト者として歩き続けるのです。ただし、以前のようにではありません。以前は、自分の足の強さで歩いていた。宗教家として、伝道者として、聖書研究者としての野心もあった。しかし、これから後は、ただただ神の恵みを頼みとして、神の栄光だけを求める者として歩き出すのです。内村鑑三はその変化について、心の中に革命が起こったと伝えています。
「彼女逝きて余の心中に革命あり、今はこの世は欲しく無之・・・・天国、復活、永生、これのみが事実にして問題に有之候」
「心の革命」という表現が、さすが内村鑑三だと思います。革命とは、たんに大きな変化が起こったということではありません。革命とは、支配者が変わることです。今まで心を支配してきたものが失せて、新しい支配者が心を支配するようになった。それが、心の革命ということでありましょう。内村はこういう詩も書いています。
余は始めは地理学者にならんと欲した。
札幌農学校に入りし時の余はそれであった。
余は其次ぎに水産学者とならんと欲した。
札幌農学校を出し時の余はそれであった。
余は其次ぎに慈善家とならんと欲した。
米国に渡りし時の余はそれであった。
余は其次ぎに教育者とならんと欲した。
米国より帰りし時の余はそれであった。
余は其次ぎに社会改良家とならんと欲した。
朝報社に入りし時の余はそれであった。
余は其次ぎに聖書学者とならんと欲した。
ルツ子を葬りしまでの余はそれであった。
余は今は何者にもならんと欲しない
又何事も為さんと欲しない、
唯神の遣わし給ひし其独子を信ぜんと欲する。
これは、腿のつがいをくじかれた痛みを忘れることができたという詩ではありません。内村鑑三は、実に才能豊かな人であった。自分の力で、十分にこの世の成功を収めることができる人であった。彼もまた、その才能を生かして神様に仕えよう、と思っていたに違いありません。しかし、愛娘を失った心の痛手は、そういう野心のすべて、また意欲や望みのすべてを、打ち砕いてしまったのです。普通だったら、ここで、「神も仏もあるものか!」と叫ぶところです。あるいは、「神を呪って死になさい」というヨブの妻の声が、心にこだまするところです。しかし、内村鑑三は、神様への信仰を棄てなかった。それどころか、益々信仰の確信を純粋なものへと高めていったのです。
|
|
|
|
|
|
それはどういうことなのでしょうか? 信仰とは、人の魂が、神様に対する正しい関係を持つことです。神様を、アラジンの魔法のランプの精みたいに、願い事を叶えてくれる人だと思い込むことは、信仰ではありません。なぜなら、神様はそういう方ではないからです。また神様が、自分の憎むべき相手をやっつけてくれる神様だと思うことも、信仰ではありません。神様はそういう方ではないのです。そのような間違った神様のイメージを抱いて、「これが神様だ」という信仰は、青空のもとでは元気がいいかもしれませんが、嵐の吹き荒れるような日になると恐れに満ち、不安にかられ、泣き言ばかりをいう信仰になってしまうのです。
そうならないためには、ほんものの神様との出逢いを大事にしなければなりません。神様について勉強したり、思いめぐらしたり、考え込んだり、定義を下したり、あるいは自分の期待を押しつけたりするようなことで、本当の神様を知ることはできません。それは、自分の手で刻んだ像を造ることと同じなのです。とても誤解されやすいのですが、信仰を持つとは、神様に対して能動的、積極的であってはいけないのです。信仰とは、あくまでも神様の働きに対する反応だからです。神様は、わたしたちの人生に様々な御業を行い、また語りかけておられます。『ヘブライ人への手紙』も冒頭に、「神語り給へり」と書いてあったのです。それに対して私たちが「ああ、神様というのはこういうお方だったのだ」とあるがままに受け入れること、それが神様の正しい理解であり、正しい関係の持ち方なのです。
たとえば内村鑑三は愛娘ルツ子が病死したとき、「ふたつの神」という文章を書いています。神様は慈悲の神、恩命の神であると同時に残酷の神であり、無慈悲の神であるというのです。神様が無慈悲であるとか、残酷であるという言い方は、厳密な神学としては乱暴な表現であるかもしれません。しかし、これは、内村鑑三が自分の知恵や勉強で言い出したことはなく、神様が愛娘を取られたという実体験に基づいた神様のイメージなのです。それでもなお、神様は神様であり、私たちが信じ、敬い、救い主として崇めなければならない神である、と確信すること、それが神様に対する信仰です。
|
|
|
|
|
|
内村鑑三は、どうして残酷な神様に出逢ったときに、神様に失望することなく、確信を深めることができたのでしょうか。それは彼が、慈悲の神に出逢った時にも、残酷の神に出逢った時にも、イエス・キリストへの十字架に望みを置く者であったからに違いありません。花を咲かせ、小鳥に歌を与え給う神は、イエス様が十字架にかかられた日、太陽が暗くなるのをゆるし給う神でありました。人々から見捨てられるような、小さき者を優しく顧み給う神は、あの日、御子に「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」と叫ばせた神でありました。正しい者を祝福し給う、と約束された神は、あの日、罪なき神の御子を罪人等の手に渡された神でありました。神様が、十字架において、このような御自身を表し給う方であると知り、そこに望みを置くとき、私たちの人生において、まったく思いがけないような仕方で出逢われる神様に対して、なお愛と恵みと確信を持ち続けることができるのです。
今日お読みしました『ヘブライ人への手紙』10章26-39節は、少し長いところですし、その中にいろいろとハッとさせられる言葉があり内容豊かなところです。しかし、その中心は35節にあります。
自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。
確信を捨てないとはどういうことか? 間違った確信は、試練の時に必ず打ち砕かれます。そういう確信をいつまでも持ち続けるのはよくありません。私たちに与えられている確信とは、十字架にかかられたキリストこそ、私たちの救いであり、そこにこそ神様の愛がこよなく現れているという確信です。どんな時にも、平和な時にも、戦いの日にも、この確信を捨ててはいけないというのです。それが私たちの持つべき信仰なのです。
|
|
|
|
|
|
そうしますと、26-31節に記されている御言葉の意味も明らかになります。《もし、わたしたちが真理の知識を受けた後にも、故意に罪を犯し続けるとすれば・・・》と、今日わたしたちに与えられた御言葉は語り始めています。もし、罪を犯し続けたとすればいったいどうなるのか? 《罪のためのいけにえは、もはや残っていません。ただ残っているのは、審判と敵対する者たちを焼き尽くす激しい火とを、恐れつつ待つことだけです》というのです。
このような御言葉を聞いて、恐れをなさないクリスチャンがおりましょうか? 私たちは自分の罪深さを知っています。私たちがもっている罪は、気がつけば改められるようなものもありますけれども、逆にどんなに気がついていても、ふとした弾みに現れてしまう、本性に深く根ざした頑固でしつこい罪というものがあるのです。《真理の知識を受けた後にも》、なおぬぐい去ることができないような罪が、確かに、私たちのうちにあります。それでは救われないというのならば、いったい誰が救われるというのでしょうか?
いや、聖書には《故意に》と書いてある。罪には過失による罪とか、状況的に追いつめられて犯してしまう罪がある。こういう罪はなかなか避けられないけれども、ここで言われているのは、そういう罪ではない。故意に犯す罪というのは、その結果をあらかじめ知っていながら、自分の意志をもって犯す罪である。逆に言えば、それは自分の意志で十分に避けられる罪ではないか。しかも、《犯し続ける》と言われている。つまり、一度や二度の過ちではなく、そういう生き方を選んでしまっているということである。イエス様が十字架にかかって、自らの命をいけにえとして神に捧げ、わたしたちのすべて罪をあがなってくださったのに、そうして新しく生き直すチャンスを私たちに与えてくださったに、そのチャンスを無にして再び以前のような罪深い生活の中に舞い戻ってしまうなら、もう弁解の余地はない、救いも残されていない。ここに書いてあるのは、そういうことであるという解釈がひとつ成り立ちます。つまり、《故意》でなければいい。故意であったとしても《犯し続ける》のでなければいい。そういうことであります。
しかし皆さん、このような楽観的な解釈は、聖書の警告を骨抜きにすることではないか、と私には思えてなりません。聖書は、これでもかと言うばかりにたいへん激しい言葉を連ねて警告を発しています。とくに29節以下では、《神の子を足げにし、自分が聖なる者とされた契約の血を汚れたものと見なし、その上、恵みの霊を侮辱する者は、どれほど重い刑罰に値すると思いますか》、《生ける神の手に落ちるのは、恐ろしいことです》というのです。このような警告を、堕落したクリスチャンに対してではなく、ある意味で真面目に平均的なクリスチャン生活を送っている人たちに向かって発しているのです。《故意》でなければいい。《犯し続ける》のでなければいい。そんな甘っちょろい警告が、ここでなされているとはとても思えないのです。
これは、イエス・キリストの十字架を無意味なものにしてしまう罪について語られているのです。10章18節には、《罪と不法の赦しがある以上、罪を購うための供え物は、もはや必要ではありません》とあります。つまり、私たちは救われるために、もはや何もしなくてもいいというのです。これがイエス・キリストの十字架による救いであるということです。だから、このイエス・キリストの十字架に依り頼んで、神様に近づこうではないかと、19-24節に言われていたのでした。
しかし、もしこの十字架の救いを無意味にするような事を語ったり、吹聴したりするならば、つまりそれは救われるためにはあれをしなければいけないとか、これをしなければいけないとか、あれをしたらダメだとか、これをしたらダメだとか、そういうことを言って自分を裁いたり、他人を裁いたりするならば、それは十字架の救いを無にすることであって、それを自らなげうつことになるのだから、《罪のためのいけには、もはや残っていません》というわけです。
それがどんなに大きな罪であるか、《神の子を足げにし、自分が聖なる者とされた契約の血を汚れたものと見なし、その上、恵みの霊を侮辱する》、それほどの大罪であるというのです。だから、自分の確信を、イエス・キリストの十字架に対する信仰を決して棄ててはいけないのです。
|
|
|
|
|
|
それは言い換えれば、信仰が変質していくことに対する警告だということもできましょう。26節に《わたしたちが真理の知識を受けた後》とありました。32節に《あなたがたは、光に照らされた後》ともあります。つまり、最初から悪かったのではなく、最初にあった良きものがだんだんと変質してしまったということなのです。
どうして信仰が変質してしまうのでしょうか。それは忍耐が足りないのです。36節にこう記されています。
神の御心を行って約束されたものを受けるためには、忍耐が必要なのです。
信仰を持つと、いろいろなことを期待するようになります。自分が生まれ変わることも、そうです。あるいは、牧師や兄姉姉妹たちに対する期待もあるかと思います。信仰者は、こうあるべきだ、教会はこうあるべきだ、いろいろなことを期待するのです。しかし、実際には、なかなかその通りではありません。牧師がだらしがないこともありましょう。先輩である兄姉姉妹達に失望させられる時もありましょう。また自分自身がなかなか成長できないことに、危機感を憶えることもありましょう。そうすると、他の手段によって、つまりイエス・キリストの十字架の道によって、自分の理想を実現しようとしてしまうのです。
もっと聖書を読まなくては、もっと祈りをしなくては、何か自分に刺激を与える本がないか、そういう集会に参加すれば心が燃えるのではないか、あるいは牧師や兄姉姉妹に対する批判になったりします。しかし、聖書はいうのです。約束されたものを受け取るためには、忍耐が必要であると。主が示された忍耐を、私たちも持つ必要があるのです。イエス様は御心をなし給えと祈りつつ、十字架にかかられました。十字架の痛み、苦しみ、汚名を着せられる恥辱に耐えられました。それは神様の約束なさったものを受け取るための主の忍耐だったのです。イエス様は十字架の死をも耐え忍ばれたのです。
そのような忍耐をもって、どんなときにも十字架の主に依り頼むことが大切なのです。決して、それ以外の手段に目を向けてはならない。それは十字架の主を足げにすることに他ならないのだというわけです。
正しい者は信仰によって生きる。
わたしたちはひるんで滅びる者ではなく、信仰によって命を確保する者です。
どうか、そのようにただただ十字架の主を見つめて、私たちの信仰を守り抜きたいと思います。 |
|
 |
| 目次 |
|

|
|
| 聖書 新共同訳: |
(c)共同訳聖書実行委員会
Executive Committee of The Common Bible
Translation
(c)日本聖書協会
Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
|
|
|