岩魚の塩焼き 降りしきる雨のなか、焚火の炎が静かに揺れ、闇が濃くなっていく。型が揃った4匹の岩魚が、不器用に削られた串に刺さってじっくりと炙られている。狩猟班長が人数分だけ釣り上げてきた源流岩魚。しかもすべてが尺前後。化粧塩が良い感じに焼けていくのを、俺達は満足げに眺めていた。(隊長) 南アルプス 信濃又河内 平成11年8月12日~15日 硬派度 ★★★★★
|
||
| 夕暮れの渓に我一人・・・。
「きたっ!でっ デカイ!!」まるで潜水艦のような姿が淵のそこからヌウッと現れたと同時に走りだした。昨日の尺岩魚より二まわり以上デカイじゃねぇか!40センチ以上かっ!こんな水量の少なくなったところにもいるのか!?源流の岩魚はツメに近づくほどでかくなるというが桁外れだ。自分の鼓動が強く早くなる。ランディングネットを掴んだが、ネットの小ささに苦笑いする余裕すらない。こちらに寄せようとするが動く根掛かりのようにまったく寄らず大岩の下に俺を引きずりこもうとする。クソッ!ラインは太くしてあるのだ!むりやり引きずり出すか!?くうっ!重てぇ!俺のロッドがグリップの先から限界までしなっている。が!ヤツは一気に走り出し、滝の下の落ちこみに流水と共にダイブした!があああっ!!
尺岩魚の感触が全身に蓄積されている
|
||
|
||
オザキ隊長からの報告 |
ナカハラ奴隷候補からの報告
|
|
 信濃俣河内。南アルプス南部・光岳と仁田岳の合間を流れ畑薙湖に流れ込む沢だ。三つのゴルジュ帯を持ち、稜線に出るまで3日を要する行程の長い名渓。 信濃俣河内。南アルプス南部・光岳と仁田岳の合間を流れ畑薙湖に流れ込む沢だ。三つのゴルジュ帯を持ち、稜線に出るまで3日を要する行程の長い名渓。沢を詰めた後は稜線を歩き、茶臼岳から南アルプス南部の大パノラマを満喫し、赤石温泉で疲れを取る贅沢な計画を目論んだ。ただし、前夜発、3泊4日の沢旅は未経験。きちんとしたエスケープルートも無いので、行動計画や装備に関しては慎重にならざるを得ない。そこで、今回は山行計画書を作成し、車のフロントに掲示。さらには、自分達に不測の事態が起きた時のみならずケガをした人に遭遇した時、救助要請できるように無線を携帯した。山行計画書には幕営予定地や参加者全員の緊急連絡先、血液型、アレルギーの有無や使用する無線の周波数などを書き込んだ。増水時のエスケープルートに関しても事前に参加メンバーで話し合い、確認し合う。 また、沢登りは登攀の要素が強いため荷物の軽量化は必須。必要以上の装備を持つことは、かえって危険なのだ。そのため、テントの変わりに防水性のレジャーシートを使用、シュラフは持たず、シュラフカバーだけで寝る。始めはテントを使わないことに不安を感じたが、慣れるとその開放感がクセになるし、何より増水に対して、素早く反応できる。  個人装備や共同装備に、どんなものが必要かは、その内どっかで詳しく書くだろうから、ここではカヌ沈的スグレモノを幾つか紹介しよう。今回、全員が使用したのは、ノースケープのエクスペディションTシャツ。極寒地用アンダーウエアだけど、コイツの保温性と速乾性は着てみればわかる。カヌ沈はオールシーズン使用している。ただし、乾燥肌の人が冬着ると、静電気で恐ろしい目にあう。それから、ノコギリはシルキーのゴムボーイ。巨大な流木も、これさえあれば安心。太ももくらいの太さなら、1分かからない。プロの大工も愛用しているらしい。折りたたみ式なので、嵩張らないところも気に入っている。冷凍・保存に使うジップロックも沢では役に立つ。完全とはいかないが、かなりの防水性があり、ハイパロンの防水バックと併用すれば、まず濡れることはない。 12日・早朝。畑薙第一ダム。 驚いたことに、ダム脇は車で一杯。お隣さんも沢支度をしている。溜息をつきながら、鮎タイツだの、特攻服まがいの作業パンツだの、パチンコに向かうオヤジジャージだの、各々てんでバラバラの格好に身を包み、ジャラモノをジャラジャラ言わせながら登山道を早足で歩く。尾根歩きの、オジチャン、オバチャンが振り返って見ている。まさに、鳴り物入りってやつだ。  林道を40分程歩き、右側の踏み跡をたどると、この日最大の難関と言えるワイヤーではなく、バンセンのぼろぼろ吊り橋に辿り着く。渡り始めて後悔したが、戻ることさえ出来ない。約10分間の恐怖。全身の毛穴は開きっぱなし。 林道を40分程歩き、右側の踏み跡をたどると、この日最大の難関と言えるワイヤーではなく、バンセンのぼろぼろ吊り橋に辿り着く。渡り始めて後悔したが、戻ることさえ出来ない。約10分間の恐怖。全身の毛穴は開きっぱなし。汗もひき、再び湖岸の踏み跡を歩き出す。暫くして、ふと足元をみるとシマシマのナメクジが渓流タビに張りついている。 「まてよ?!やすさん、これって・・・・」 「うっげえ、ヤマビルだあっ!お、俺にも・・・」 「うぎゃあああ」と、ナカハラ。 凄い勢いで、無数のヤマビルが次々と這い上がってくる。手で弾くと、手に吸いつこうとする。恐ろしい奴だ。小走りで河原に降り立つが、ナカハラの絶叫は暫く続いていた。さすがに信濃俣河内。なかなかの歓迎ぶりだが、水線に辿り着けばこっちのものだ。初日の幕営地までは、明るく開けた河原歩きが続く。なんとなく北アの梓川に似た感じがする。晴天の沢登りとは、こんなにも気持ちがいいものなのか。いつも雨に祟られるカヌ沈にとって、これほど嬉しいことはない。  やすが、さっそく小さい淵に潜る。無邪気だ。あまりにも楽しそうなので、俺も横澤のゴーグルを奪って、水と戯れる。型の良いアマゴが数匹。頭の中で、井上陽水の”少年時代”が流れている。「昔は楽しかった・・・」などとはほざかない。 カヌ沈は今だって、最高に楽しいのだ。
焚火が本格的になりだした頃、石を飛んでやすが帰ってきた。その姿、天狗の如き。 |
朝の清々しい空気に感謝しつつ始まった今回の南アルプス信濃俣河内の渓流登山。晴れ渡る曇りなき青空は、山への恐れと不安が入り混じり複雑な心境であった僕の心を、これから始まる三泊四日の素晴らしい「川遊び」への期待へと高めてくれていた。素晴らしい旅が始まりそうだ。 体力的な不安があるため装備をかなり軽くしていく。
沢での昼飯はソーメン 定番だ 心地よい沢の音、河原の広がった空間、そしてその両側を覆うようにして広がる木々、そして何よりも青空。何もかもが素晴らしい。途中にちょっとした淵を見つけるとそこで休憩。ヤスさんは獲物を求める狩人のように目を光らせ潜り、狙いを定めている。隊長とヨコサワさんは水遊び。幸せなひと時である。そしてまた沢を遡っていく。
尺岩魚を釣り上げていたのだ。バックから取り出した岩魚。でかい。1匹は尺以上は余裕で超えている!狩猟班長ここにありである。早速岩魚汁にする。 身がぷりぷりしていて旨い。これだけで夕飯が豪華になる。沢の恵みに感謝。
流木倒木が沢を塞ぐ これが鉄砲水の原因のごく一部 |
|
| 翌朝 カヌ沈にしては珍しく早朝の出発。ゴルジュのど真ん中でのビバークだけは避けたいからだ。  今日は三つのゴルジュ帯を突破しなければならない。最初のゴルジュ帯で先行者が、釣り糸を垂らしている。昨日、俺達を瞬時にして追い越して行った強者二人組みだ。そのうちの一人に、見覚えがあった。ヒマラヤニストの松原尚之さんだ。マカルー(8463M)東稜初登攀やK2(8611M)など数多くの登攀クロニクルを持つ日本屈指のクライマー。 今日は三つのゴルジュ帯を突破しなければならない。最初のゴルジュ帯で先行者が、釣り糸を垂らしている。昨日、俺達を瞬時にして追い越して行った強者二人組みだ。そのうちの一人に、見覚えがあった。ヒマラヤニストの松原尚之さんだ。マカルー(8463M)東稜初登攀やK2(8611M)など数多くの登攀クロニクルを持つ日本屈指のクライマー。 その松原さん、第二ゴルジュ帯で俺達の写真を数枚撮っていた。物好きな人だ。そのうち、「沢で見かけた変な人達」とか言う見出しでどっかの雑誌に掲載されたりして・・・。そうこうしているうちに、またもや、風のように抜き去っていた。癪なので、負けじと同じルートを辿るが、無理はするもんじゃない。滝壷のトラバースでやすが力尽き、絶叫しながらドボン。かく言う俺は、もっと最悪。落ちることもできず、クライムダウンもできない達磨状態。対岸から這い上がったやすのシュリンゲに救われる。なんとか最難関の第三ゴルジュ帯も突破し、幕営地を探す。雨脚が強くなってきたので、増水しても安全な苔むした高台にシートを張る。焚火番をナカハラにまかせて、狩猟班長について狩猟に勤しむ。といっても、俺は釣らない。博打でいうところの”見”というやつだ。すぐに8寸くらいのサイズがヒット。今日はなんとしても塩焼きが食いたい。その後も、次々にヒット。しかし・・・強引に引き抜こうとするので、最後の最後にバレてしまう。やっと2匹目を取り込んだと思いきや、ポーチに入れようとして、またもや逃がしてしまう。嗚呼、塩焼きが・・・。もう見ていられない。悔しすぎる。やすを残して、幕営地に戻り、怒りを横澤とナカハラにぶちまける。これ以上、暗くなると危険になる頃、やすが帰ってきた。一人になってから、「釣りに集中できた」と言い、ポーチから その松原さん、第二ゴルジュ帯で俺達の写真を数枚撮っていた。物好きな人だ。そのうち、「沢で見かけた変な人達」とか言う見出しでどっかの雑誌に掲載されたりして・・・。そうこうしているうちに、またもや、風のように抜き去っていた。癪なので、負けじと同じルートを辿るが、無理はするもんじゃない。滝壷のトラバースでやすが力尽き、絶叫しながらドボン。かく言う俺は、もっと最悪。落ちることもできず、クライムダウンもできない達磨状態。対岸から這い上がったやすのシュリンゲに救われる。なんとか最難関の第三ゴルジュ帯も突破し、幕営地を探す。雨脚が強くなってきたので、増水しても安全な苔むした高台にシートを張る。焚火番をナカハラにまかせて、狩猟班長について狩猟に勤しむ。といっても、俺は釣らない。博打でいうところの”見”というやつだ。すぐに8寸くらいのサイズがヒット。今日はなんとしても塩焼きが食いたい。その後も、次々にヒット。しかし・・・強引に引き抜こうとするので、最後の最後にバレてしまう。やっと2匹目を取り込んだと思いきや、ポーチに入れようとして、またもや逃がしてしまう。嗚呼、塩焼きが・・・。もう見ていられない。悔しすぎる。やすを残して、幕営地に戻り、怒りを横澤とナカハラにぶちまける。これ以上、暗くなると危険になる頃、やすが帰ってきた。一人になってから、「釣りに集中できた」と言い、ポーチから尺前後の4匹を取り出す。 絶句のち絶叫。山の恵みに感謝しながら、 骨までしゃぶり尽くす。その味たるや、言わずもがな、である。 |
2日目が始まる。 徐々に沢の岩が大きくなり、渓谷らしい風景となる。岩から岩へ跳ねていくのが楽しい。そしてゴルジュ。 ゴルジュの突破こそが僕にとっての沢登りの一番の楽しみである。 |
|
沢のツメはこのように急登となりかなりツライ
なぜここで死んだのか?鹿の白骨 |
岩魚の上のシャモジと大きさを比較してもらいたい |
|
| 岩魚や山女を食うことを、疑問視する人も多いと思う。 絶滅に近づいている危惧種であることは、承知している。今、この国で岩魚や山女が群れる渓がどれ程存在するだろうか。苦しい言い訳をさせてもらえば、「だからこそ、食うのかもしれない」。と、言うと誤解されそうだが、その貴重な命を奪う時にこそ、命を奪われし渓魚と、その美しい渓魚を育てた山-もっと言えば、森-に感謝し、敬い、そして自らの心の傲慢さを呪詛するのだ。詭弁と言えば詭弁。今の俺達は、そこまで言うほどの思想は無い。  正直に言えば、容易に人を近づけない自然の、可逆性の範囲であることを願いつつ、この環境・風景を持続させていく為に「自分達にできることは何か」を模索することしか、今はできない。例えば、「キャッチ&リリース」は「自分達にできる”何か”」ではあると思うが、それに満足していけない、と俺は思う。あくまでも、始めの一歩なのだ。岩魚や山女にだけ感心を寄せ、その命を生み出す”母なる森”を見ないのでは、 正直に言えば、容易に人を近づけない自然の、可逆性の範囲であることを願いつつ、この環境・風景を持続させていく為に「自分達にできることは何か」を模索することしか、今はできない。例えば、「キャッチ&リリース」は「自分達にできる”何か”」ではあると思うが、それに満足していけない、と俺は思う。あくまでも、始めの一歩なのだ。岩魚や山女にだけ感心を寄せ、その命を生み出す”母なる森”を見ないのでは、いずれ渓魚達は、絶滅するだろう。 岩魚を食った後は、文字どうり消化試合のようなもの(勝手に消化試合にされてしまった出来事については、深い哀悼の意を表したい)。当然にして、南ア南部の大パノラマなど見えるはずも無く、あとは、ナカハラの膝がぶっ壊れようが、激しい雨に打たれようが、金も無いのに山小屋に泊めてもらおうが、
茶臼岳山頂 2604m 無事に帰ってきたからすべて良いのである。 |
日が沈みかけたところでやっと帰ってきた。そして力強くひと言。 「一人一匹食えれば十分だろう」 そう、なんと4匹も源流岩魚を釣り上げてきたのだ。しかも一匹は 尺をさらに越える大物である。狩猟班長はまさに狩猟班長であった。オーラすら出てるようである。 山の神様とヤスさんに感謝である。
血を流している。
茶臼小屋で死亡中のナカハラ奴隷候補 それを思いやる狩猟班長 お金もわずかしか無く、汚れきった僕らを山小屋の主人は暖かく迎えてくれた。お金は下山して送付することにする。疲れきった体に山小屋の食事と寝床はありがたく、救われた思いであった。僕らを受け入れてくれた山小屋の方々には言葉では言い尽くせないほどの感謝である。 「カヌ沈隊養老部」。先を行く隊長達は 「ドバミミズ隊」である。今回装備として持ち込んでいた無線で連絡を取り合いつつ下りて行く。そのやり取りがなかなか楽しい。 山への恐怖から、自分の体力への不安から、そして精神力の弱さから弱気になる場面が何度もあったと思う。しかしそれらは全てメンバー強さによって助けられ、陽気さによって救われた。本当に感謝である。 |
|
炊事班長の番外編 (例によって報告書の遅い炊事班長は番外編にて・・・。)
「信濃俣河内」なんて素晴らしい響きだ。炊事班長はこの南アルプスの沢に一種の憧れと何か女性的な魅力を感じていた。 |
||




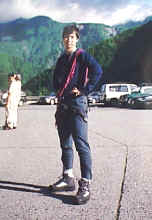









 滝の流れと深い淵、そして両側を覆い隠す巨大な岩の壁。とても美しい景色であり、自然との戦いの場でもある。試行錯誤しつつ突破していく。
滝の流れと深い淵、そして両側を覆い隠す巨大な岩の壁。とても美しい景色であり、自然との戦いの場でもある。試行錯誤しつつ突破していく。
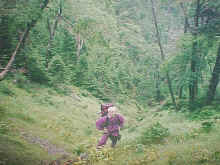




 かなりの出血だ。しかし手当てをするとまたすぐに登り始める。いつまで続くか判らないこの沢の詰めで止ってる余裕はないのだ。ヤスさんも心配をかけまいとしている。
かなりの出血だ。しかし手当てをするとまたすぐに登り始める。いつまで続くか判らないこの沢の詰めで止ってる余裕はないのだ。ヤスさんも心配をかけまいとしている。