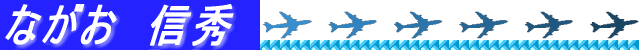| 1 |
採択された意見書 ◎は政審発議、○は委員会発議、●は自民会派発議・民主会派発議 |
|
| ◎ |
地方財政の充実・強化を求める意見書 |
| ◎ |
B型肝炎問題の早期全面解決を求める意見書 |
| ◎ |
外国資本等による土地売買等に関する法整備を求める意見書 |
| ◎ |
一般国道の維持管理の充実を求める意見書 |
| ○ |
精神障がい者に公共交通機関の運賃割引制度適用を求める意見書 |
| ○ |
重症心身障がい児(者)への支援に関する意見書 |
| ○ |
口蹄疫など家畜の感染症に対する備えを万全にするよう求める意見書 |
| ○ |
森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する意見書 |
| ○ |
道路の整備に関する意見書 |
| ○ |
義務教育の機会均等の確保と教育予算の確保・拡充を求める意見書 |
| ● |
小林千代美衆議院議員の議員辞職を求める決議 |
| ● |
荒井聰衆議院議員の事務所経費疑惑に関する真相解明と説明責任をはたすよう求める決議 |
|
|
※「小林千代美衆議院議員の議員辞職を求める決議」、「荒井聰衆議院議員の事務所経費疑惑に関する真相解明と説明責任を果たすよう求める決議」の2件は、
自民会派が提出した。民主会派は、その内容、手続きが妥当性を欠き、党利党略を地方議会の場に持ち込むものであるとして反対した。
|
|
   |
|
ながお信秀代表格質問の要旨 (○は質問者発言、●は答弁者発言)
|
|
1
|
「北海道モデル」について
|
| ○ |
任期が残り1年を切った中で突然に示された「モデル」と、知事公約に基づく「新生プラン」等との関係は。 |
| ● |
「北海道モデル」は、「新生プラン」や「ほっかいどう未来創造プラン」の実現に向けて、北海道の優位性や特性を活かすことができる分野において、北海道の活性化や国全体の発展につなげようとするもの。 |
| ○ |
策定に際し、市町村や関係団体からの意見は、どのように聴取したのか。また、道民からの意見聴取、パブリックコメントの手続きを必要としないとした理由は。 |
| ● |
総合計画や新生プランを踏まえた施策であり、パブリックコメント手続きはとらなかった。今後も北海道経済政策戦略会議や総合振興局、振興局を通じ意見集約していく。 |
| ○ |
国への「モデル」の提言はどう進めるのか。また、国の構造改革特区や道州制特区との関係はどう整理するのか。 |
| ● |
国費予算要望等の機会を捉え働きかけていく。権限移譲や規制緩和については、それぞれの特区の仕組みを最大限活用し、実現を図っていく。 |
| ○ |
具体的な「モデル」の施策展開の手法は。 |
| ● |
それぞれの「北海道モデル」ごとに関係機関が連携し、さらに地域や民間の人材、資源、アイデアを集め、展開を加速していく。 |
| 2 |
財政運営について
|
| (1) |
今後の国の地方財政運営について |
| ○ |
国の23年度予算の編成に向けて、最優先で何を求めるのか。 |
| ● |
「経済の活性化や雇用の確保・創出」、地域医療提供体制の確保等、「安全で活力ある地域づくり」、「環境と調和した社会の形成」に重点を置く。 |
| (2) |
一括交付金について |
| ○ |
「一括交付金」が、23年度から段階的に制度化されようとしている。道への交付金の使途を庁内で、どう決定していこうとするのか。 |
| ● |
配分に向け、客観的な指標、社会資本整備進捗率や財政力の強弱、地方実情への配慮等を、国に提言。庁内での決定方法は、国の動向を注視し情報収集に努めていく。 |
| 3 |
北海道の自治のすがたについて |
| (1) |
支庁制度改革について |
| ○ |
いまだに知事が地域に入ることが実現されない中で、地域には、道庁組織がわかりにくくなったとの声もある。現状認識と、積み残されている課題への対応は。 |
| ● |
残された課題について理解が得られるよう、地域との信頼関係の構築に努めていく。 |
| ○ |
地域に大きな混乱をもたらしている出先機関の組織名称変更の影響への認識は。 |
| ● |
新名称が浸透するよう、地域づくり連携会議を通じ、地域振興に取り組んでいく。 |
| ○ |
市町村との融和をどう図り、信頼回復をどのように図ろうとしているのか。
|
| ● |
全道振興局長会議で、「信頼関係構築に向け努力するよう」指示するとともに、知事が地域を訪れた際に、同様趣旨を職員に訓示している。 |
| (2) |
市町村合併について |
| ○ |
平成の市町村合併の総括は。 |
| ● |
住民サービス向上、公共施設の広域的利用、行財政運営効率化や基盤強化に効果がある一方で、住民の一体感の醸成が図られない、重複施設の統廃合が進まない、廃止された住民サービスがある、といった課題が生じた。 |
| 4 |
当面する道政課題について |
| (1) |
経済対策について |
| ○ |
中長期的な方策を検証し、成長分野や支援策など、今後の経済政策のあり方が検討されているが、官民の役割分担、とりわけ道としての果たすべき姿が見えてこない。 |
| ● |
新たな健康関連産業の育成や、省エネ・新エネ事業の推進等に取り組んでおり、戦略会議を通じ、中長期的な観点に立った取り組みについて議論を深めていく。 |
| ○ |
どのように本道の優位性を発揮し競争力を高めるのか、そのためには道内の中小企業果たす役割、雇用の創出を具体的に示すべきだが。 |
| ● |
「健康」「環境」「国際」の3つの視点を重視しながら、相談指導体制の整備や資金供給の円滑化等により、中小企業の経営基盤の強化を図る。また、新規事業展開や新分野進出を促進することにより、雇用の維持・創出を図っていく。 |
| ○ |
信用保証協会の経営強化も含め、中小企業者の厳しい現状をどう打開するのか。 |
| ● |
金融支援制度が効果的に活用されるよう、金融機関や信用保証協会に対し、積極的な取り扱いを要請。また、商工会議所・商工会等と連携を一層密にし、中小企業の経営支援に万全を期す。 |
| (2) |
雇用対策について |
| ○ |
雇用創出基本計画で、22年度の目標数を2万8,500人とした考え方と、達成に向けた今年度の雇用戦略の考え方は。 |
| ● |
雇用関連交付金の効果的な活用により目標を設定。3つの視点での産業振興の取り組みや、人手不足分野の解消に向けて全庁的な取り組みで重点的に展開する。 |
| ○ |
「ふるさと雇用再生特別対策事業」「緊急雇用創出事業」については、実効性をあげるために、市町村や受託事業者がより運用しやすくなるような制度改善や、基金の追加造成等の必要がある。 |
| ● |
雇用就業機会を確保するため、切れ目のない対策、実効性がある取り組みが必要。国に交付金の追加交付、人件費割合等の事業要件の緩和について要望していく。 |
| ○ |
職業訓練の対象職種・業務のメニュー見直しに、どう取り組んでいるのか。また、一次産業への就労促進に向けた訓練メニューを強化すべきだ。 |
| ● |
医療・福祉分野、一次産業における人材育成に向けた委託訓練を実施。一次産業就労に向けては、農業大学や漁業研修所、森林整備担い手支援センターにおいて実践的な研修に取り組んでいる。 |
| ○ |
季節労働者を取り巻く状況の変化をどう把握しているのか。 |
| ● |
公共事業の縮減、景気の低迷により厳しい状況が続いている。
|
| (3) |
医療・福祉対策について
|
| ○ |
道立病院では、「北海道病院事業改革プラン」を策定したが、経営は改善せず、経営形態の見直しも全く進展していない。早急に計画を見直すべきだ。 |
| ● |
道立紋別病院の地元移管に向け努力しており、他の道立病院の経営形態の見直しについても、指定管理者制度の導入の可能性を含め、条件の検討を進めている。 |
| ○ |
道立紋別病院の移管は難航しているが、何が課題で、今後どう解決していくのか。 |
| ● |
財産譲与では病院に関わるものについて無償譲渡、財政支援策では5年程度の分割交付、職員支援では2年間の自治法派遣を基本的な考え方として整理している。 |
| ○ |
広域化・連携構想を促進するためにも、地域の中核的病院に対して、地方交付税による措置や道による積極的な財政支援を行い、その中核的病院から医師を派遣するシステムを構築するべきと考えるが。 |
| ● |
地域医療再生基金を活用して、中核的な医療機関の医師確保を図るため、医育大学からの指導医派遣システムを構築するとともに、総合内科医の要請事業に取り組む。 |
| ○ |
高齢者施策の地域連携パスは、疾患の発生から診断、治療、リハビリ、在宅医療までを、複数の医療機関、施設にまたがって作成するケース計画が必要になっている。道が主体的に参画、市町村、医療機関の協力で早急に体制を作り上げるべきだ。 |
| ● |
「地域包括支援センター」において、ケアマネジャーが医療職との連携を促すための機能強化に向けて検討を行うとともに、研修を通じてケアマネジャーや主治医に対し、医療と介護の連携の重要性の周知を図りながら、切れ目のない支援を図っていく。 |
| ○ |
北海道の高齢化率が、全国平均を上回る伸びで推移している中で、介護保険制度運用に係る見通しと講じるべき対策への所見は。 |
| ● |
低所得者対策や介護職員の待遇改善の国への要望、ケア体制の中核的機関である地域包括支援センターの機能強化、介護予防の推進、認知症ケア体制の強化等、安心して暮らすことができる社会の構築に向けて積極的に取り組んでいく。 |
| ○ |
道が、介護予防に関する専門的スタッフを組織し、医師、保健師、社会福祉士等が支援する体制をつくり、市町村における専門性を高めていくことが必要だ。 |
| ● |
保健師や栄養士、歯科衛生士等を構成員とする支援チームを設置、介護予防事業従事者の資質向上や、事業の企画立案に対する助言等、支援強化に努めている。 |
| ○ |
「北海道障がい者条例」が4月から本格施行されたが、道庁全体での取り組みを加速させ、条例に基づく取り組みについて道内外に発信、提案していくべきだ。 |
| ● |
シンポジウムやタウンミーティングで、道民に広報・啓発してきた。体制整備では、「地域づくり委員会」設置や「地域づくりコーディネーター」配置、また入所施設事業を地域生活支援型事業に転換させる取り組みを、全国に先駆けてスタートさせた。 |
| ○ |
障がい者が権利や人権の擁護を求めたり、地域で自立して生活する場合において、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家の協力は不可欠だ。こうした団体に対し、どう要請し、どう協力体制を構築して障がい者の権利擁護に取り組んでいくのか。 |
| ● |
弁護士会からは、「地域づくり委員会」の委員を推薦いただいた。必要に応じ、司法書士や行政書士等の専門家にも参加していただく。 |
| (4) |
一次産業振興について
|
| ○ |
戸別所得補償制度のモデル事業が動き出した。制度の評価、農業者意見の把握は。
|
| ● |
モデル事業は、生産者の経営の安定を図る上では有効な手立ての一つ。自給力向上事業については、従来の制度に比べ、単価設定など地域の主体性が働きづらい。本格的な制度設計に向けて、水田農業の持続的な発展が図られるよう努める。 |
| ○ |
戸別所得補償制度の畑作への拡大について、今後国にどう意見を伝えるのか。
|
| ● |
将来にわたり意欲と希望を持って営農に取り組める制度となることが重要。生産者の経営努力が適切に評価される制度設計に向けた考え方を、国に政策提案した。 |
| ○ |
補償政策の対象となっていない酪農、畜産、野菜、果樹の分野に対する、経営安定策、所得政策についての見通しと道の対応は。 |
| ● |
将来にわたって所得が確保され、意欲を持って営農に取り組むことができる仕組みとなるよう、国に積極的に働きかけていく。 |
| ○ |
6次産業化に向けて、農産物を加工し、販売し、サービスを提供する等の事業展開についての課題をどう捉え、解決のための施策展開をどうするのか。 |
| ● |
「食クラスター連携協議体」の活動を基本に、農産物の持つ機能性に着目した取り組みや、農商工連携ファンドを活用した事業化支援を積極的に推進していく。 |
| ○ |
6次産業化の実現のためには、食品加工、外食産業、流通業との連携は欠かせない。連携を支える人材の確保、育成にどう取り組むのか。 |
| ● |
産業支援機関に配置しているインキュベーションマネージャーに、新たに産業間連携による販路拡大の機能を加える等して、人材の確保・育成に努める。 |
| ○ |
北海道が、東アジア地域への輸出拠点としての展望を開くためには、情報提供や輸出促進の取り組みに、道としてのリーダーシップが求められているが。 |
| ● |
流通ルート開拓や、ネット販売事業者と連携したモデル事業実施に加え、「北海道国際ビジネスセンター」において、中小企業に対し、貿易に関する個別相談や海外取引に関するマッチング支援を行っている。 |
| ○ |
口蹄疫対策として、農家・農場の侵入防止対策への支援をどう進めているのか。夏の観光シーズンを迎えての、侵入防止対策の進め方は。 |
| ● |
農場入り口における消毒の励行に努めるとともに、空港等における靴底の消毒実施、ポスターの掲示等により、水際対策に取り組んでいる。 |
| (5) |
交通確保対策について |
| ○ |
HACの今後の経営案の策定に際して、日航の会社更生計画の推移によって、日航との関係そのものが成り立たない、あるいは、ごく短期の支援・協力にとどまる可能性を想定しているのか。 |
| ● |
日航の会社更生計画にHACへの支援が盛り込まれるよう強く働きかけていく。 |
| ○ |
HACへの道の経営責任については、これまで以上の責任が発生する等の厳しい事態も想定して、事業プランを検討していかなければならないが。 |
| ● |
事業プラン案の取りまとめにあたっては、HACが安定的に事業運営を継続できるよう、日航からの支援を強く求めるとともに、札幌市をはじめとする関係機関との連携・協力のあり方を検討する。 |
| ○ |
国や札幌市、就航先の空港がある函館市、釧路市等の自治体をはじめとする各機関と、HACへの支援について、どう今後の協議を進め、理解を得ようとするのか。 |
| ● |
関係機関からは、具体的な事業計画の説明を受けた上で対応を検討するといった対応が示されており、経営体制の基本的考え方や、事業収支試算を示しつつ調整していく。 |
| ○ |
丘珠空港の存続は、道内の経済活動や地域間交流に多大な影響がある。事業プラン策定にあたり、これらの影響をどう受け止め、どう対応しようとするのか。 |
| ● |
第三者機関によるHACの試算査定においては、移転費用等の初期投資額が大きくなることから、交通アクセス確保の課題が指摘された。「新しいHAC経営体制の基本的な考え方」については関係機関と意見交換を行い、事業プラン案を取りまとめる。 |
| ○ |
道新幹線の、函館市での新駅と現駅との安定的アクセスは、同市のまちづくりの根幹にかかわり、札幌延伸に向けた重大な課題と考えるが、事態への認識は。 |
| ● |
並行在来線の経営分離への沿線自治体同意は、整備新幹線の認可着工の基本条件とされており、このアクセス問題は早期に解決しなければならない課題だ。 |
| ○ |
地域意向が十分に配慮されるようJR北海道と積極的に協議、最大限に努力すべきだ。 |
| ● |
並行在来線問題についてJR北海道や沿線自治体と意見交換・協議していく。 |
| (6) |
男女平等参画について |
| ○ |
男女間の雇用における待遇の格差解消の成果についての検証状況は。 |
| ● |
20年度末の道内の女性の平均賃金は、男性に比べ約7割で、依然として格差がある。 |
| ○ |
男女間の雇用待遇、賃金格差解消について、具体的な数値目標を立てるなど、第2次計画の実効性ある推進策が必要だ。 |
| ● |
国で男女の均等な機会や待遇の確保についての検討が進められており、国の計画の内容を見極めながら、指摘の点も含め基本計画の見直しについて検討する。 |
| 5 |
教育課題について |
| (1) |
教育行政のあり方について |
| ○ |
教職員の服務規律等実態調査は、道教委自らが違法性を認めているようなものであり、調査・分析を即刻中止すべきである。 |
| ● |
調査を通して、教職員の服務規律の状況や職員団体の活動による学校運営への影響について明らかにするとともに、正すべきことは正し、適切な学校運営を行うことができる環境を整えることが大切だ。 |
| ○ |
調査が、新年度の多忙な時期に強行され、現場からは、子どもたちと接する時間や本来業務の時間が削られたとの厳しい批判や不信の声が出ている。こうした事態を生じさせた責任についての所見は。 |
| ● |
教育公務員として法令を遵守していくことが何よりも必要だ。調査を行うことが学校教育に対する道民の信頼の確保につながると考える。 |
| ○ |
情報提供制度、通報制度は、教育員同士の「密告」を固定化させるものだ。教職員間の不信や疑心暗鬼をあおり、教育の基盤である信頼を学校現場から失わせるような制度は取り止めるべきだ。 |
| ● |
本制度は、情報提供の対象を法令違反行為に限定するとともに、情報提供者に対しては、原則として氏名・連絡先を明らかにし、客観的な事実に基づいて情報提供を行うこと、誹謗中傷を目的とした情報提供をしてはならないことを定めている。 |
| ○ |
本制度で、保護者や地域住民に何を求めようとするのかが、全く理解できない。単に教育や学校に対する疑心暗鬼や不信をあおるだけのものになると危惧する。 |
| ● |
情報提供の対象は、学校運営及び教職員の服務に関し、法令や学習指導要領に違反する行為に限定している。 |
| (2) |
特別支援教育について |
| ○ |
「特別支援学校の配置に関する考え方」の素案策定の前提として、「特別支援教育」への転換後、「障がいのある子ども」が急激に増加したのはなぜかという分析がない。また、「障がいのある子どもたち」を「特別支援教育」の枠組みだけで捉え、普通教育との連携という観点が考慮されていないが。 |
| ● |
障がいの有無に関わらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し、共に支え合う社会の実現を目指すことは重要。小中学校の要請に応じ、特別支援学校から、パートナーティーチャー派遣事業や、小中学校の教育を対象とした各種研修に取り組んでいる。 |
| ○ |
素案には、「障がいのある児童生徒」や保護者の負担増が懸念される対応が盛り込まれている。「できるだけ身近な地域」ではなく、「身近な地域・通学区」での就学を実現すべきだ。 |
| ● |
校舎の狭あい化への対応や高等部における受入体制の整備、児童生徒数の少ない視覚障がいや聴覚障がいの特別支援学校における集団性の確保が急務と考えている。 |
| (3) |
フッ化物洗口について |
| ○ |
インフォームドコンセントでは、危険性の情報提供も不可欠であり、保護者が子どもの最善の利益を判断して、承諾、または拒否する権利を保障しなければならない。 |
| ● |
安全性に不安を持つ人もおり、洗口の安全性や適切な実施方法について、保護者に対して十分に説明した上で、希望した子どもに対して実施する。 |
|
再質問 |
| 1 |
「北海道モデル」について |
| ○ |
任期最終年だ。知事が積み残した多くの課題から、優先的に実現すべき課題としてテーマ設定したわけではないのか。今年度の道の予算執行、施策展開で、6テーマをどう取り扱うのか。 |
| ● |
地域の特色ある取り組みを、さらに磨き上げていくための先導的事業の実施等、モデル全体を牽引していくような取り組みに、予算を効果的に活用するとともに、率先して関係団体に働きかける。 |
| ○ |
実現への意欲に疑問が持たれる対応だ。各部局横断的に取り組むとしている6テーマを設定した際の庁内での協議の経過は。テーマは、今後も増やすのか。 |
| ● |
関係部局で検討、政策会議で決定した。障がい者条例に基づく先導的な取り組みを踏まえ、「共生型事業」への総合的な支援等、福祉分野も新たに加える。北海道経済政策戦略会議や総合振興局、振興局を通じて道民の意見を聞き、モデルの充実に努める。 |
| 2 |
北海道の自治のすがたについて
|
| (1) |
支庁制度改革について |
| ○ |
地方に混乱を持ち込んだにもかかわらず、成果は乏しいと言わざるを得ない。知事自らが地域に出向き、知事自身が信頼回復を図る努力をする姿が見えない。積み残し課題の解決と、信頼回復こそが最優先されるべきではないのか。 |
| ● |
道庁が地域と一体となった取り組みを進め、自ら地域に出向くことにより、地域との実りある関係づくりに取り組んでいく。 |
| (2) |
市町村合併について |
| ○ |
知事として、道としての総括が全くない。平成の大合併終了に際しての総括は。 |
| ● |
合併効果が発揮されるよう助言や支援していく。今後は、自主的な合併や広域連携の取り組みについても助言や支援を行い、市町村の行財政基盤や機能強化に努める。 |
| 3 |
当面する道政課題について
|
| (1) |
中小企業経営支援について |
| ○ |
中小企業の新規分野参入等を重視するならば、新規事業に対する補助率アップ、貸付金利の緩和等の支援策強化が検討されるべきだ。 |
| ● |
中小企業応援ファンドによる製品開発や販路開拓事業の補助率引き上げ、中小記号総合振興資金による創業貸付の自己資金要件や事業確信貸付の対象要件の緩和により、支援の強化を行っている。 |
| (2) |
雇用対策について |
| ○ |
雇用交付金事業の効果として期待されているのは、継続的な雇用創出。地域での取り組みが継続的な事業となっている実績と、継続的な事業促進のための支援策は。 |
| ● |
「ふるさと雇用再生特別対策推進事業」では、244事業が22年度にも継続的に実施されている。地域会議や「常用雇用一時金」の活用を通じ、雇用の受け皿づくりに取り組む。 |
| ○ |
季節労働者の通年雇用促進への方針転換による通年雇用化の実績は。 |
| ● |
各年度5千人程度を目標として、19年度は5,137人、20年度は5,466人の通年雇用化が図られた。 |
| (3) |
一次産業振興について |
| ○ |
戸別所得補償の本格実施に際し、畑作農家が安心して経営を営むことができるために、道はどう取り組もうとしているのか。 |
| ● |
交付金の支援水準の確保に向けて国に強く働きかけていく。 |
| ○ |
「食クラスター連携協議体」が成果をあげるために、解決すべき課題と対応は。 |
| ● |
庁内横断的な体制や、地域ごとの連携体制を整備してきた。 |
| (4) |
北海道新幹線について |
| ○ |
札幌延伸に伴う並行在来線の対応への考え方は。 |
| ● |
経営分離区間については、地域の意向を十分に配慮する必要があり、今後もJR北海道とも率直な意見交換を行っていく。 |
| 4 |
教育課題について |
| (1) |
教育行政のあり方について |
| ○ |
服務規律等実態調査の意義は。 |
| ● |
教職員が服務規律を遵守し、学習指導要領に基づいた指導が行われ、適切な学校運営が行われることが目的。 |
| ○ |
情報提供制度、通報制度は、極めて時代錯誤的な発想。この制度によって、教職員が互いに信頼しあい、適切な学校運営が本当に行えると考えるのか。また、地域、保護者との信頼感が醸成されると考えるのか。 |
| ● |
信頼関係の大前提は、法令の遵守である。本制度の適切な運用により、信頼の確保に資するものと考える。 |
| ○ |
学校運営への不満、教師への不満を、こうした制度によって助長することは、地域、保護者、学校現場での相互不信を、いたずらにあおると懸念するが。 |
| ● |
学校現場に無用の混乱を招かないよう、情報の内容を判別、適切に制度運用していく。 |
| ○ |
学校に関る課題は、学校の主体性によって解決されるのが基本。学校の頭越しの通報制度は、論理矛盾。中止を含め、制度を見直すべきだ。 |
| ● |
情報提供の内容や信ぴょう性を精査した上で、当該市町村教育委員会と連携を図ることにより、学校運営の適正化につなげていこうとするものだ。 |
| (2) |
フッ化物洗口について
|
| ○ |
危険物の懸念も含めた情報提供が必要であり、学校現場の教職員の理解が、導入の大前提となるべきだ。 |
| ● |
保護者への説明会に先立ち、効果や安全性、実施方法について教職員に説明を行うことにしている。 |